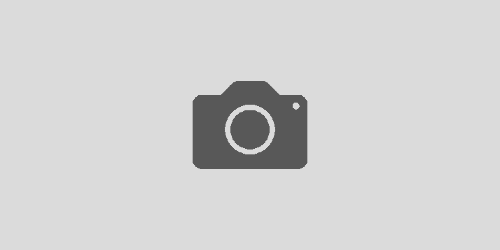令和のいろは(2025.3 歌舞伎座 通し狂言 仮名手本忠臣蔵)

2025.3 歌舞伎座 通し狂言 仮名手本忠臣蔵
雪で始まった忠臣蔵の月
この雪が一度では終わらず、さすがは忠臣蔵、雪すら降らせるなどとおもっていたら
先日は三月なのに25度を超えまして夏日を記録しました。気候が激しすぎる。
劇場では花道に物を置いて係の人に注意される人を観測しました。
たまにくる人が多い出し物のときだけある光景。
歌舞伎座で見たのはとても久しぶり。
チケ松満席の日も相当あり、実際大層な賑わいでした。
2階ロビーには判官と由良之助の衣裳の展示もあり。
1階外の売店には忠臣蔵絡みのお菓子がずらり。
13年振りの歌舞伎座通し、国立の全通しから数えても9年?
コロナがなければもっと早くかなったのでしょうか
昼:大序、三、四、落人、夜:五、六、七、十一の構成。最近東京ではこれが多いようです。
座組は、Aプロ、Bプロと分かれていて、昼夜で由良之助が入れ替わる組み合わせとなっています。
切符買うときカレンダーとチラシを見比べながらかぶらないように確認しながらで大変。
B夜、A昼夜、B昼夜で見ました
今回は成田屋も高麗屋も出ない。播磨屋もいない。
由良之助役者として(さらに取りまとめとして)仁左衛門の存在が大きく、
大役を任される中堅以下がそれぞれ頑張って大きな空白を埋めています。
見たことがある忠臣蔵の中にちょこちょこ見慣れないやり方がが入り込んできながら今月のステージができあがっていて、
自分が何も知らない昔に考えていたような、親から子へ厳格に型が伝わり西は西、東は東…なーんて世界ではないんだなと
あっちゃからこっちゃに伝わってまた戻ってきたり、ミックスしたり、御家庭の料理みたいに時につれ変わっていくものなんだなと実感しています。
経緯が理解できる通し上演や、心の機序が見えるようなやり方がお客さんに好まれる時代な気もしており、それは仁左衛門の歌舞伎とも通ずるものがあって、令和的な、”わかる忠臣蔵”が生まれていたように思いました。
実は、自分がいちばん本心から共感できたのは
最後の最後に「してしてかたきは?」と尋ね首尾を聞いた菊五郎服部のパッと華やぐ顔でした。
朝からのすべての中で、ここにいちばん実感できる本当があるような。
我々は当事者になることはできず、毎日ニュースを見ながらどうなったのかと気をもむ一傍観者である。
可能であれば少しでも関わりたいと思う気持ちもあるかもしれない。
そんな我々と同じ目線のひとが舞台の上に居るようで、なにか、とてもわかるものがありました。
幕切れの仁左衛門と菊五郎の印象で朝からの全てが上書きされつつ、見て良かったなと実感して帰れる忠臣蔵でした。
判官、勘平については菊之助、勘九郎とも受け継ぐべき人が受け継いだという印象。
愛之助は怪我から復帰。客席から見る限りは全く問題なさそう。
もう1人の由良之助松緑は自身の手がけた新作のような、昔ながらのようでいてもしかして新作?みたいな雰囲気をまとっているのが印象的でした。
以下はメモ。大変長くなりました。
推敲するのに毎度上から読み始めて七段目くらいで挫折してしまうため、最後が怪しいです(笑)
[stoc]
口上
幕開きの10分前から口上人形による配役読み上げ。開場も少し早め。
従来はこれがあることは不文律でどこにも書かなかったものらしいのですが(←ということが国立の通しのときのセミナーに書かれております)、さすがに書かないと現代の観客には伝わらないという判断か、10分前から口上人形が出ることも、四段目はいわゆる「通さん場」であることもWEBサイトに親切に案内されておりました。良いと思います。
「とーざーーい」の後、口上人形が幕の間から出て、当日の役名と役者の名前を読み上げ。最初は菊五郎。(でも出るのは最後)
聴いて欲しいところや看板役者のときには、エヘンエヘンの咳払いや、繰り返しの読み上げがあります。
お客さんは読み上げられる全員に拍手してましたが、途中読み上げ速度の速いところがあって、無理だ、おいつかねえってなった。バラエティ番組の高速エンドロールみたいなものですかね。知ってる知ってるって名前が来たら拍手したくはなります。
最後は仁左衛門。「そのため口上左様」で終わる。
11月にこの読み上げリアルバージョンを立川のセレモニーで聞きましたが、「なーーーかむら」っては言ってませんでした。普通だったw
大序
ゆーっくりと幕が開きます。非常に長いです。本来柝を47打つというのはここ?(古書によると、なんでも現代の劇場は間口が広すぎて47回では足りないとか)
この芝居は四十七や七五三にちなんだものがあれこれあるそうですが
最初は、全員お人形なので、うつむいて目を閉じた状態から、七、五、三で顔を上げるのだと、ずーーっと昔に読みまして
七、五、三って、どういうこと?ってわからなかったんですが
今回Aプロではそうやっていたようです。
まず足利直義・扇雀が顔を挙げた後
師直・松緑は七拍を等分で小刻みに顔を上げる。若狭之助・松也はぎ ぃぃぃぃと扉が開いて止まるような五拍。なんだか装置感があって良い。
判官・勘九郎はすぅぅと三拍。
言い伝えは本当だったんだ、みたいな気分になりました。
Bプロは違っていて、芝翫・師直が六拍くらい。右近、菊之助は拍がわかりませんでした。
で、新田義貞のかぶと(後醍醐天皇から賜ったもの)を奉納しようというお話に若狭之助は同意、師直が苦言。
B芝翫の師直はナチュラルな”目上の嫌な人”。
A松緑は少し漫画チックにやってるかもしれません。若狭之助はA松也、B尾上右近。
直義公がおっしゃるには兜が47個落ちててどれが新田のだかわからないから全部拾ってきたと。(ぉ、おぅ)
大将はじめ47人討ち死にしてるイメージの想起から始まるんですね。
見分ける役目として判官の奥方の顔世御前が呼ばれる。Aプロ孝太郎、Bプロ時蔵。
顔世ちゃんは、かぶとがご下賜されたときの係だったからわかる。焚きしめた蘭奢待の香りでもわかるとのこと。(うん。そしてけた違いに派手派手なかぶとだから間違わないねコレ。)
家によって兜はまちまちだという義太夫の説明の「家々」の詞に合わせて首を横に振る顔世さん。否定のいえいえかな、細かい。
いろいろあって。でっかい結び文を持って顔世に言い寄る師直のところへ通りかかって助け舟を出すナイスガイ桃井若狭之助のキャラクター性が際立ちます。
孝太郎顔世は退場のときの涙を堪えた様子が、セクハラつらかっただろうなと思わせて、これは流石に共感。
時蔵顔世はわりかしメンタル強そう。
距離の残り20cmくらいの言い寄り方にふんわりとリアルなイヤさがあるのは芝翫だったので、芝翫と孝太郎の組み合わせだったらもっといやだったかもしれない。
今回はここで終わらず、師直が判官と桃井に、退出が早いのどうのと呼び止めて戻らせたりする嫌がらせがあって、ぴきぴきする桃井。
了見の若い皆さんが刀を抜きかけて、何らかの理由で止められるのを何度も見せられるのが忠臣蔵という芝居だと、今回思い知りましたが、そのトップバッター。
怒り度は松也のほうが高いかな。右近は歌舞伎らしい大きな振りをしていて絵的です。
判官はクッション役。ここまででは次に降りかかる火の粉には思いも及びませんが、我々は知ってるので、あぁぁぁと思いながら次へ。
三段目
進物
桃井さんちの家老、加古川本蔵が師直に進物をしにくるところから。
ある意味気の付く家来よな。(コンプライアンス違反であるが)
二段目が見たいですよね。九段目と一緒にやるとかないかな。
通しだと意外といっぱい出る鷺坂伴内、Aは松之助、Bは橘太郎。
そうか、これとあの道行に出てくる伴内は一緒か、と急にシナプスが繋がったり。
家来達との「ばーっさり」の練習のくだりが、松之助は右足を踏み出すのを合図にで、橘太郎はエヘンばっさり。
これが全然違って面白い。
賂もBの橘太郎は袖の下が入るように、脇を開けて停止しており、本蔵はややあって気づく感じ
Aでは本蔵がいそいそと働いて、伴内側は思いがけず貰った風に見えました。
松の間
殿中刃傷のところ。巻いてある茣蓙をダーッと投げてごろごろごろっと敷くやつ(出投げ)に観客拍手。
若狭はあんなに怒ってるのに、本蔵のおかげで事なきを得て、代わりに急に師直からの風当たりの強くなる判官。
そこから刃傷に至ってしまうまでがあっという間に思えました。
昔見たものは、鮒侍のくだりなどもっと耐えがたい時間だった気がする。私が今回の師直のやなところを受け止め切れてないのか。
周りの侍に止められる判官は勘九郎のほうが大きく脇を開閉する形で様式的に見え、菊之助はわなわなしてました
この幕が閉じた後は太鼓が鳴らず、あれ?みんな席立ってる。ああ幕間か。って感じ。(意外と太鼓を頼りにしているのだった)
しばらく小さく三味線が鳴り続けています。幕三重というそうです。
幕間が入るときにこうなるのは記憶にない。
イヤホンガイドでは今月出ない幸四郎が演目に関する知識を喋ってくれています
しばらくしてまた三味線が再開すると四段目になります
四段目
足利の上使が来て御家断絶と判官の切腹が言い渡されます。
石堂はAプロは良心の梅玉。Bプロは沈着な彌十郎。
判官の亡骸に扇を載せて上意の書状を置く所はAは扇をそのまま、Bは刀の鍔あたりに当てて要を外してから置いていました。
薬師寺はシングルキャストで彦三郎。
この人はいちばん歌舞伎だったかもしれん。塩冶側の事情を全く考慮しないデリカシーなき様子が良い。異様な声のデカさがそのまま異質さになっています。
力也は莟玉。赤みのない化粧でいちばん青ざめたような顔してました。額のくりが大きめで幼く見えます。
四段目の由良之助はA仁左衛門。B松緑。
Aのときは花横ブロックでしたが前の人が大きくてセンターがあまり見えなくてですね。隙間から仁左衛門を見ると勘九郎が見えない。勘九郎を見ると仁左衛門が見えない。
四段目で真ん中が見えないのは致命的。
(というわけでAプロ少なめでごめん)
判官がこれは形見…の後2回目に言う「か、た、…」を勘九郎はか た きと無声音だが発声している
これは意外でした。伝える意思ある言葉。
菊之助はか、た、の後はむっと口をつぐんで発声せず。
先に書いたようなわけで仁左衛門由良さんが判官の衣服を整え、九寸五分を握った指をゆっくりひとつずつはずすさまなどはさぞやと思いながら隙間から部分を見ておりました。
菊之助・松緑はバディ感があり、主君なんだけどお友達が死んじゃったみたいにも思えました。
焼香の所では、孝太郎の顔世は髪を落としてきたことを言っていたように思いますが(うろ覚え)、時蔵は語ってなかったのかな。切った髪がそれとはっきりわからなかった。
乗り物を送って、残った組頭達との評定になります
原郷右衛門はAB共に錦之助。適役。ずっと由良之助と心を共にし絶対信頼できるイメージ。
斧九太夫は片岡亀蔵。七段目に再登場のときも同じ配役で、諸士もそうですけど続きを見られるのが良いところです。(ただ、ABで由良之助の配役が捻れるので、同じ日に同じ組み合わせにはならないのだ)
仁左衛門の由良之助は流石にこの人に説得されれば信服せざるを得ないものがあります
松緑の由良之助は諸士と年齢の近い管理職で同志を説得する雰囲気がある
(一方で仲間から見て批判もしやすく、七段目での疑いにも繋がるのかなと)
屋敷の明け渡しのときはABとも、表門を青竹でバツじるしにして閉門。
上方のやり方です。
門外に詰めかけて来ている家中の者達。これを組頭達が抑えるの、ちょっといいですよね
伝わったんだなって思えて。
先頭切って来てる莟玉の力弥が幼く見えて、あんたまでどうしたのって親戚モードになりました
皆が引き揚げると由良之助独りとなります。暁烏を聴いて提灯を消し、本体だけをはずし、畳んで袂に入れる。塩冶の家の形見ともみえます。提灯に描かれた鷹の羽紋をじっと見る仁左衛門が目に残ります。
屋敷が遠ざかるのは元の道具が斜めになり少し遠くなる程度
(何段も小さくなるやつは無し)
松緑の由良之助は判官が亡くなって以降ところどころ涙を溜めていましたが、この花道で屋形を振り返り、がたっと崩れて弱さを見せます
最近の松緑は、ひとり、思いを噛み締めて花道をはいったり、幕切れで舞台に残されたりするときが良いなと思う。今回の振れ幅激しい三役では由良さんが好きです。
落人
ここまではちょうど今の季節なんですね
戸塚から見る小さめ富士山と菜の花と桜
Aでは、みっくん鷺坂がとんぼ返ってた
すごいすごい。←それ最後だけどな
あ、えーと、あ、そうそう、清元に延壽大夫いた
…えーと…ごめん、ちょっと気が遠くなってました
止めても止めても死に取り憑かれてるように思えたのはB愛之助勘平だったなあ
五段目
ここから夜
昼は抹香でしたが、夜は火縄や提灯や手紙を燃やす匂いが舞台から時間差で自席に到着します。
山崎街道鉄砲渡し
勘平はA菊之助、B勘九郎。ここは同日で同じ役者が判官と勘平にならないようになっています。
菊之助勘平と萬太郎千崎の間にはよく知ってる同士の雰囲気が漂います。
火を貸しながら住まいを聞き出す所は一旦話を留めて矢立を準備してから書き始める
巳之助の千崎は話を続けながら準備していた。
この千崎は堅そうで、六段目で(撃ち止めたのは)「舅であろうがぁっ!」って一喝するやり方も合いそう。(あれ、勘平かわいそうなんよな。)
二つ玉
定九郎、A尾上右近
稲藁から出る手が真っ白くて映える。
お金は袋の中で探るだけで数えないようです。
歩き方が武家のダンディーな定九郎でなく田舎のごろつきに見えました。
こういう定九郎が原点に近いのかもね。山賊をしてるっていうくらいだから。
血はきれいに右足腿に。
Bプロは隼人。
こちらは典型的な定九郎に見えましたが、着物の裾を搾るところが、ふわぁとしていて、そんなちょっとで大丈夫かー。もっとしぼってー。
(ここは正月の團十郎が上手かった。濡れてずっしりしている着物がわかる。)
お金は枚数を数えるやり方。(2回目に見た時には枚数数えてるかどうかはわからなかった)
鉄砲は音だけの後、花道でもう一度撃ついつものやり方。
定九郎が撃たれた後、時を遡って勘平の視点からもう一度同じ時制を見せている説が自分はしっくりきています。
六段目
Bは松之助の源六が上方のやり方なので、全体的に上方の雰囲気が勝ります。。
いちめんにめんさんめんしめんごめん、と言って勘平の前を通ったり、おかるの駕籠にいまから振ること覚えてどないすんねん、等。
勘九郎・勘平も義太夫風の台詞回しにしているようです。お才は魁春。
Aは橘太郎の源六で江戸風。お才は萬壽で、千崎が萬太郎。勘平は菊之助。ここまで揃うと見慣れた菊五郎劇団のリズムになり、少し懐かしくなりました。
源六の”ご安心”はABともあり。Aはまだ載せるものがあるよーと間違えて煙草盆を掲げるのがありました。
不破はABとも歌六。Aは傷をあらためるとき指示していたかも(うろ覚え)。
おかるはA時蔵、B七之助。母おかやはA吉弥、B梅花。
おかやの印象で場の雰囲気が変わるところはある。
吉弥はちょっと武家っぽいかも。時蔵おかるも腰元だったのがわかるよう。
梅花はちいさいかわいらしいおかあさんです。
Bの勘平・勘九郎を2回目に見た時、おかるが退場してからが怪談かと思うような雰囲気で、少しびびりました。
1回目はここまでAと雰囲気違わなかったと思うなあ。
二人侍が来た時から様子が顕著にかわる。
はっきり自分で刀を抜いて鏡にして髪を整え(ここで見得までする)
表に案内を乞うものがある旨をおかやに話す勘平は表情が乾いて死んでいる。
物言わんとする姑を刀の鞘で抑える力の強さは侍への妄執なのか。
色に耽ったばっかりにの自嘲は大袈裟め。血糊の色は紫がかっている赤。(歯医者さんで歯垢の検査に使う色)
少なめで、指の痕が見えるくらいでした。
疑いが晴れたことを確かめる所はやっと嬉しそうに。だがこの先がやばい。
血判の前には激しく腹を一文字にぐぐぐと切るので、血判押す時はほぼ力尽きて伏せており千崎の力で押している。
せん妄らしき表現、死の間際の痙攣など、ちょっと怖い。
最期の「かる…かる」も前は微かに聞こえるか聞こえないかくらいだったのが、はっきり3回くらい言っていました。
これが勘九郎のやり方になるのでしょうかね。
もの凄いと形容されるのはまちがいなく、コクーンにあったようなヒリヒリするものがあるように思います。
Aの勘平は菊之助。
菊五郎が言っていた、六段目は勘平の財布があっちにいったりこっちにいったり段取りが大変というのを思い出してしまいました。
そしてこれは知ってる勘平だけど、昔見たような美しい勘平というのでもなかった。
勘平の情けなさがわかるようになったのは自分が大人になったのか。
七段目
一力茶屋。
鬼ごっこの掛け声は、「(休)ゆらーおーにゃー|(休)まだーいのー(休|休)てのーなーるー|ぅほおーぉへ」のようなシンコペーション。
“鬼さんこちら”で思い浮かべるリズムとは違うもの。仁左衛門で以前にやったものの録画を見たら随分ゆっくりとしていました。
見取りでやるときは見立てのあそびがありますが、今回はなし。ここから芝居が始まるわけではないし、その先もあるという事で要点にしぼったんでしょうか。
三人侍は赤垣・松江、富森・男女蔵、矢間・亀鶴。
四段目から続いて出てくるのを初めて認識しました。富森さんは割と顔で語ります。
平右衛門A巳之助、B松也。
由良之助はA愛之助、B仁左衛門。
この段は流石に仁左衛門のものですね。
愛之助の寝たふり由良さんは、巳之助の平右衛門が畳にそっと置いた願書を扇でばしゅっと的確に打ち返していて、平右衛門のいる所にちゃんと来るのが可笑しかった。
仁左衛門のは適当に飛ばすのを松也・平右衛門が拾いに走る感じ。
由良之助の性質の違いが見えるよう。
愛之助は遊んでいても堅い。
仁左衛門は軽みがありながら、一瞬見せる本心の表情の鋭さが別人級です。蛸肴の後の「おのれ…」のところや、力弥が訪ねてきたときの一瞬で真顔になるところなど。
夜の部の力弥はABとも左近。ちょうどいい大きさ、真面目さ、かわいさ。よいなあ。
(この力弥だと小浪と娶せてもままごとのようなもので儚くてかわいそう。
莟玉の力弥だと年恰好がガチっぽくてそれはそれでかわいそう。)
平右衛門は先に松也のを見て、見慣れない現代っぽいやり方に感じたので、巳之助はもっと形式っぽいかなと思いましたが、あまり違わなくて、元は同じやり方らしい。
みっくんは筋書で前回浅草のとき仁左衛門に習い三津五郎のやり方も取り入れていることを語っています。
松・巳2人の少しの違いや、そもそもの型はどこからきたのかは紀尾井町家話で言ってましたが、この番組は中身を書かない約束なので困る。
もったいないので松緑サンはいつかちゃんとまとめてほしい
おかるは引き続き時蔵と七之助。
七之助は2回見たのですが、2週間あけたらめざましく綺麗になっていて、わずかの間に変わるものですね。
兄妹のじゃらじゃらの所はABとも短めで、三回くらいでしたか。
このくらいなら耐えられる
斬りつけられたおかるが懐紙を投げて散らす時
松也は七之助が綺麗に散らした懐紙の舞う中を刀を振って抜けてくるよう。
正月の歌昇はおかる(児太郎)が纏めて投げたのを刀を当ててバラす方式にしていてこれも綺麗でしたが
時蔵巳之助組は二つの中間のように見えました。
巳之助と松也で顕著に違うのはおかるに斬りつけた後、おかるをなだめすかして刀を置くときで、松也は大刀を置いて、まだ小刀が腰にあるのをおかるに指摘される。
巳之助は大小をまとめて置いてしまう。これは見たことがない。案外察しのいい巳之助お兄ちゃんです。
あっちゃむいてるときは松也は腕を水平に拡げて拳を下に向けており、巳之助は腕組み。
勘平の死を知ったおかる。七之助は後ろに反って真っ白になる。反りすぎて背中が殆ど地面についてた。一瞬で衝撃が突き抜けたんでしょうね。それから起き上がって癪が起こる。
時蔵は前のめりになってじわじわと言葉が浸透するようになって癪が起こる。理解するまでの時間をこちらも感じるよう。
実は長年なんだろう?と思ってたのが
癪で苦しむおかるに対する平右衛門の「のっちゃあならねえ」の繰り返し部分
ひたすら、のっちゃあなんねえを繰り返すタイプの平右衛門もいて、おまじないか何かみたいに聞こえてました。
今回は巳之助、松也共に、「のるなのるな」を基調にたまに「のっちゃあならねえ」が混ざる感じでした
「のる」は「反る(伸る)」ですかね
妹の発作が楽になるように声を掛けながら一生懸命に介抱しているおにいちゃん。
普通にそういう場面なんでしょうが、ほぼ初めてそういう実感を持って見ました
今まで見た芝居では、まだ斬る気が満々なのを隠した平右衛門が怖がるおかるを騙し騙し呼び寄せているように感じてしまったのですが、今回はおかるにちゃんと説明をして本当のことを明かして、他人の手にかかるよりは自分でという意味がよりわかりました。
お正月の『まねてみます』を見たせいかもしれませんが何度も見た七段目の仕組みが今頃ほどけた感じです。
『みぃんなウソウソ』のおかるは手紙を残らず読んで理解したから由良之助の偽装放蕩がわかっていてそう言うのだし、
平右衛門が、お手を煩わせずとも自分でと空に向かって勝手に喋ってる所では、
由良之助は聴いているかも知れず、平右衛門は万にひとつそこへ届けと喋っているかもしれないと思いました。
(…きっとそうではなくやっぱり思い込みの激しい兄貴が勝手にやってると見えるのがいいんだろうけど)
前半の日程で見た時は、松也・七之助が実に歌舞伎らしくない兄妹で(…意見には個人差があります)、えーと…ってなりましたが、後半の日程ではそこに突っ込ませない引き込まれる芝居でした。
歌舞伎らしくなったわけではないんですが、しどころらしくなったというか、実の見える好きな平右衛門です。
大星とおかるが九太夫を刺すところは、おかるを上へ呼んで上から刺す型
最後の最後に大星が九太夫を打ち据えるとき
愛之助は地面で、仁左衛門は座敷で。
義太夫の通りなら地面なんでしょうね。(23日に見た時は仁左衛門も地面だった)
#今回は梯子を縁の下に倒して塞いでおくのはなかったです
その間、Aプロの巳之助平右衛門と時蔵おかるは俯いてる。居ない人になってます。
Bプロの松也平右衛門は身体を起こしたまま控えており、仁左衛門の仕事を穴の開くほど見てる
見るともなく見ているのではなく、ご家老の一挙手一投足見逃すまいとまじまじと見ている。
あまりにも見ているので、こちらもマジマジ見てしまいました。
ところで、Aプロのとき、私の隣の人、ずうううっと笑ってました。
七段目のあれこれは笑えるところもあるけれどそこまで笑えるかな。それもAプロで。(そういうテイストの違いがある座組だったんですよ。)
予想外のことが起こった時にひとは笑うものらしいので、全部予想外だったのか。もしかして。
今回は九段目は出ず、すぐに十一段目です。この幕間が10分。お手洗いに立ったら戻ってこられなそうなので、座って待ち。
十一段目
表門
山鹿流の陣太鼓、仁左衛門は七拍子。どん、と大きく打った後小さく六。松浦の太鼓の時と一緒です。
愛之助は六拍子。こんなとこに差が出る不思議
なお、この陣太鼓は架空らしいので正解はない模様。
広間の場面はなし。
奥庭
落ちていく女中たちを見逃してやる力弥(左近)の風情が立派です。
泉水の立ち回り、Aは年長組。小林は松緑、竹森は坂東亀蔵。
また見られると思ってなかったんで嬉しい。
例のしゃがんで跳躍しながらの振りは亀蔵は剣道の素振りのように脚を入れ替えずにこなしていました。流石にきついんだろか。
代わりに(?)吼えて威嚇し合うさまが威圧感有り。
松緑小林は橋の上に倒れ込んでも背中で息がわかりました。お疲れさまでござる。
Bの小林は萬太郎。対する竹森は橋之助。
若さゆえの剣の速さがあります。ごろんごろんと投げ合うところも楽しい。(橋之助のラジオによれば、首投げと巴投げ)
小林は大きな人の役という先入観がありましたが
(私の小林原体験は團蔵さんなのだ。でかくて鋭くてこわいのだ。)
萬太郎は小兵ながら手練れで、被衣をかざした牛若丸のような連想もあり、こんな小林もあっていいのかとうれしくなってしまいます。時々ギロっと横目で見るところが良い。マハーバーラタのビーマを思い出させます
こちらは倒れた後に息してたりはしない。若いな。
炭小屋本懐
槍をつける前の二人は歌之助と廣太郎だと思うんですががんばって古風な言い回しをこなしている感があふれていました。若い。
師直は首になると小さいですね。
皆さまざまに何かをかみしめていますが、見える範囲でかなり泣きにはいってたのが菊市郎。
最後方、最下手に平右衛門がいます。
この人だけ袖なしで鬘も八方割れで、四天のイメージなんだろうと思いますが、四天じゃなくて陣羽織くらいの幅がある。Bの松也は肩幅が広くて頭ひとつ出てるし目立つことといったら。
で、そこにいるとわかってるのでAのときみっくんを探したけど、どこやぁってなってしまった
再度B見たら、やっぱり松也平右衛門、どーん。面白いなあ。
忠臣蔵らしい勝ち鬨で一旦浅葱幕。
引き揚げ
正面の花水橋の向こう(舞台奥)から、引き揚げてくる大星、首を槍先に掲げた大鷲(歌之助)が見え始めると感慨があります
太鼓橋なので最初頭だけが見える
だんだんに見える人数が増えてくる
舞台の道具のよくできているところです
迎える服部逸郎はABとも菊五郎
乗馬での登場で、馬に乗ったまま声を掛けます。
一瞬で空気が変わるというか、夜が明けたよう。
浪士達のことを気にしていたであろう事が2言3言と表情に見て取れるのだもの。
力弥を先頭に銘々が花道を引き揚げ。
すべての浪士が引き揚げて、大槌(掛矢)を肩に背負った平右衛門が、槌に結んだ血染めの縞の財布を示して揚々と去ると
大星由良之助だけが残され、服部との会話あって、
最後は大星の引き揚げを服部が馬上で扇を掲げて見送って幕です
ありがてえありがてえ
ディテールを調べようと古書をひっくり返していたら、戦後初めての昭和22年の忠臣蔵通しの劇評が出てきて、当時の七代目幸四郎の大星について「近代劇の手法を以て、チョボや送り三重のある『忠臣蔵』に挑んでいるのである」(戸板康二 今日の歌舞伎)とやや批判的ニュアンスで書かれていました。
80年前で既にこの記事ですが、今年のこの上演にもそう思われることがいくつかありました。もうそちらが優勢になるのを止められないかもと思ったりもする。歌舞伎は生き物だし。でも今回を忘れないうちに次は別の家のやり方で又かかるといいですよね。
先の本には当時として久しぶりの通しがこれほど話題になるとは思わなかったことや、昔は誰もが段取りや台詞を知っていたけど、いまは研究者や古老の解説書が珍重されていることなども書いてあり、全く現代と重なってて面白いです。程度が全然違うのでしょうけどね。
(この時は大序、三、四、落人、五、六、七、九で10:30-20:30だそう。裏門が見たい旨が書いてありました。私も見たい。
あと、我々が見たような十一段目の立ち回りの手はまだできていないはず。)
少し前に、忠臣蔵や新薄雪物語で歌舞伎座を大入りにしたいと松竹の戸部さんが話していましたが
とりあえず、忠臣蔵の大入りは果たされたっぽい
個人的には、いま忠臣蔵で人が呼べるのか懐疑的だったので、蓋を開けてのこの賑わいに、さすがすぎるやろ忠臣蔵、と思っています。(2025.3.31 junjun)

配役
昼の部
通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)
大序 鶴ヶ岡社頭兜改めの場、三段目 足利館門前進物の場、同 松の間刃傷の場
四段目 扇ヶ谷塩冶判官切腹の場、同 表門城明渡しの場
浄瑠璃 道行旅路の花聟
夜の部
通し狂言 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)
五段目 山崎街道鉄砲渡しの場、同 二つ玉の場
六段目 与市兵衛内勘平腹切の場
七段目 祇園一力茶屋の場
十一段目 高家表門討入りの場、同 奥庭泉水の場、同 炭部屋本懐の場、引揚げの場
<大序・三段目>
【Aプロ】
高師直 松緑、塩冶判官 勘九郎、桃井若狭之助 松也、鷺坂伴内 松之助、加古川本蔵 橘三郎、顔世御前 孝太郎、足利直義 扇雀
【Bプロ】
高師直 芝翫、塩冶判官 菊之助、桃井若狭之助 尾上右近、鷺坂伴内 橘太郎、加古川本蔵 橘三郎、顔世御前 時蔵、足利直義 扇雀
<四段目>
【Aプロ】
大星由良之助 仁左衛門 、塩冶判官 勘九郎 、顔世御前 孝太郎 、薬師寺次郎左衛門 彦三郎 、赤垣源蔵 松江 、富森助右衛門 男女蔵 、矢間重太郎 亀鶴 、小汐田又之丞 橋之助 、大鷲文吾 歌之助 、佐藤与茂七 宗之助 、勝田新左衛門 吉之丞 、大星力弥 莟玉 、斧九太夫 片岡亀蔵 、原郷右衛門 錦之助
、石堂右馬之丞 梅玉
【Bプロ】
大星由良之助 松緑 、塩冶判官 菊之助 、顔世御前 時蔵 、薬師寺次郎左衛門 彦三郎 、赤垣源蔵 松江 、富森助右衛門 男女蔵 、矢間重太郎 亀鶴 、小汐田又之丞 橋之助 、大鷲文吾 歌之助 、佐藤与茂七 宗之助 、勝田新左衛門 吉之丞 、大星力弥 莟玉 、斧九太夫 片岡亀蔵 、原郷右衛門 錦之助
、石堂右馬之丞 彌十郎
<道行>
【Aプロ】
早野勘平 隼人 、鷺坂伴内 巳之助 、腰元おかる 萬壽
【Bプロ】
早野勘平 愛之助、鷺坂伴内 坂東亀蔵 、腰元おかる 七之助
<五・六段目>
【Aプロ】
早野勘平 菊之助 、女房おかる 時蔵 、千崎弥五郎 萬太郎 、斧定九郎 尾上右近 、判人源六 橘太郎 、母おかや 吉弥 、一文字屋お才 萬壽 、不破数右衛門 歌六
【Bプロ】
早野勘平 勘九郎 、女房おかる 七之助 、千崎弥五郎 巳之助 、斧定九郎 隼人 、判人源六 松之助 、母おかや 梅花 、一文字屋お才 魁春 、不破数右衛門 歌六
<七段目>
【Aプロ】
大星由良之助 愛之助 、寺岡平右衛門 巳之助 、赤垣源蔵 松江 、富森助右衛門 男女蔵 、矢間重太郎 亀鶴 、大星力弥 左近 、仲居おつる 歌女之丞 、鷺坂伴内 松之助 、斧九太夫 片岡亀蔵 、遊女おかる 時蔵
【Bプロ】
大星由良之助 仁左衛門 、寺岡平右衛門 松也 、赤垣源蔵 松江 、富森助右衛門 男女蔵 、矢間重太郎 亀鶴 、大星力弥 左近 、仲居おつる 歌女之丞 、鷺坂伴内 橘太郎 、斧九太夫 片岡亀蔵 、遊女おかる 七之助
<十一段目>
【Aプロ】
大星由良之助 愛之助 、小林平八郎 松緑 、竹森喜多八 坂東亀蔵 、赤垣源蔵 松江 、富森助右衛門 男女蔵 、矢間重太郎 亀鶴 、木村岡右衛門 玉太郎 、大鷲文吾 歌之助 、大星力弥 左近 、勝田新左衛門 吉之丞 、佐藤与茂七 宗之助 、杉野十平次 光 、近松半六 竹松 、倉橋伝助 廣太郎 、織部弥次兵衛 桂三 、寺岡平右衛門 巳之助 、原郷右衛門 錦之助 、服部逸郎 菊五郎
【Bプロ】
、大星由良之助 仁左衛門 、小林平八郎 萬太郎 、竹森喜多八 橋之助 、赤垣源蔵 松江 、富森助右衛門 男女蔵 、矢間重太郎 亀鶴 、木村岡右衛門 玉太郎 、大鷲文吾 歌之助 、大星力弥 左近 、勝田新左衛門 吉之丞 、佐藤与茂七 宗之助 、杉野十平次 光 、近松半六 竹松 、倉橋伝助 廣太郎 、織部弥次兵衛 桂三 、寺岡平右衛門 松也 、原郷右衛門 錦之助 、服部逸郎 菊五郎