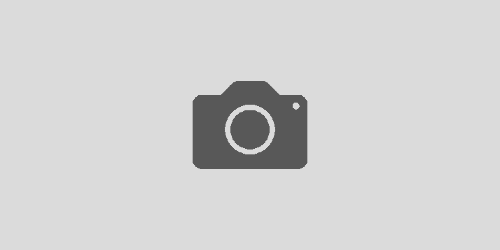2025年9月に見たもの(仮名手本忠臣蔵二段目・九段目、菅原伝授手習鑑通し)

九月が暑いのはもう慣れっこですね。
歌舞伎座での菅原伝授手習鑑通しと、国立劇場主催の忠臣蔵の珍しい幕の上演で、見たことがないものを見る楽しみのある月でした。
[stoc]
もくじ
歌舞伎名作入門「仮名手本忠臣蔵」 (新国立劇場中劇場)
「歌舞伎名作入門」と題して新国立劇場中劇場で行う国立劇場の主催公演の2年目。
昨年はあった「未来へつなぐ国立劇場プロジェクト」の冠が取れていて淋しいです。
今回は3月歌舞伎座の忠臣蔵通し上演ではかからなかった二段目、九段目をピックアップ。
加古川本蔵にスポットを当てた上演で、この抽出の仕方だとだいぶいい役です。
梅玉は仮名手本忠臣蔵の加古川本蔵は初役だそうで、1月の裏表忠臣蔵の安宅の関になぞらえた本蔵と合わせ技で本蔵完結編。
二段目 桃井館力弥使者の場 同松切の場
滅多に出ない話です。春の忠臣蔵通しの時に幕間のイヤホンガイドで話を聞いて、いつか見たいものだと思っていましたが、まさか年内に叶うとは。
今月は歌舞伎名作入門なので、忠臣蔵にちなんだ口上人形が解説をします。
なんと二体。口上太郎以外に口上次郎がいたとは知らなかった。太郎は大きなたれ目、次郎は浅黒くて男らしい顔をしてます。
肩衣には国立劇場の紋。声は虎之介、玉太郎。
国立劇場名物、でっかい相関図もあり、黒衣さんが指し棒を扱ってました。
舞台袖で幕をたくし上げた小屋っぽい方式も定着
ああ、普通の花道があればねー(って、あと8年くらい言わなきゃいけないらしいよ。)
さて本編。
本蔵/梅玉、戸無瀬/扇雀、力弥/虎之介、小浪/玉太郎、若狭之助/鴈治郎
鶴ヶ岡八幡宮の後で、松の間の前の話。
何かあったことはもう桃井の屋敷にも伝わっています。
明日早めに来てね、と、口上を伝えに、塩冶の家老大星由良之助の息子である大星力弥がやってきますが、
そんな時なのに本蔵は諸事情で口上の取次役を妻の戸無瀬に任せ、戸無瀬は義理の娘の小浪に任せます。なぜなら力弥と小浪は許婚者だから。
扇雀がやるとそんなぽやっとした母ではないように見えるのですが、この辺からもう戸無瀬の勘違いぶりが発揮されてて、この価値観が後々につながるのですね。
小浪は玉太郎。力弥の近くに寄って口移しで口上をとかわけわからんことを言います。決まった台詞なので仕方ありませんが、絶妙にイラっとさせる小浪で、おーまーえーはーってなる。
が、そこは力弥、きちんと扇で線引きしての御口上。
虎之介はさすがパンフで自負する通りの力弥役者で凛々しげです。
殿様、桃井若狭之助は鴈治郎。
本蔵1人に、師直を斬ろうと思うので止めるなよと打ち明け、
本蔵はおやりなさいの意味で松の枝を切って見せる。
いつも殿様の相手をしていていなし方がわかってるのでしょう。殿様は決意の顔で今生の別れのつもりで就寝。
(ここ、3月の時の役者でも見たかったですね。怒り冷めやらぬところから二段目へ突入したらもうピキピキしてるでしょう)
ですがそこから本蔵はいきいききびきびと働き出し、品物を用意させ、目録をしたため、妻子の止めるのも聞かず、いざ館へという所で幕。まるで戦さのよう。
かっこいいんですよ。やってることが賄賂でも。
梅玉が良いと信じてやっていることが悪なわけないというね。
だけどこれはやっぱり裏かな
この後判官が腹切ったら本蔵を褒められないものね。
この後三段目の師直の館前の所に続くわけですが、それも上演してしまったらおかしいですかね?
何しに出て行くかわからないままに幕になるので、知ってるとは言えもうちょっと見たい。
桃井もしくは加古川の家は
後で山科へ押しかけてしまう戸無瀬もそうなんだけど、自分から動けば道は開けると思っているきらいがある。
ただ、事態が特殊すぎる。
九段目 山科閑居の場
由良之助/鴈治郎、お石/門之助、一力亭主寿助/寿治郎
ほかは二段目と同じ
今度は芝居の前に口上次郎が喋ります。途中ものすごく色々あるので初見で解説なしだと厳しいでしょう。口上人形はよい手ですね。
さて、さっき若狭之助だった鴈治郎が大星になって出てくるという通し狂言あるある。
確か昔見たようなと思いましたが、あの鴈治郎はお父さんだったんだな。
話の流れとしてはついに一力茶屋から由良之助が帰ってきたということですね。
祇園から店の衆を連れて雪玉を転がしてくる。
妻のお石は心得たものでご祝儀を渡し、力弥は雪玉を裏へ転がしてゆきます。つべたそう。
一方で、赤い着物の戸無瀬と白無垢の小浪が由良之助の所に尋ねてくる。
しかしお石とは激しい温度差があります。
門之助が、まさにカチカチのお石。半分本心なのでは。
戸無瀬も割合固めです。小浪は衣裳の捌きが心許ない。頑張れ。
いつもは割とここの女たちのやり取りがメインのように思いますが、今回は本蔵が現れてから俄然面白くなります。
本蔵の本心を見抜いていた由良之助と、仇討の準備ができていると踏んで婿引出を持ってきた本蔵の会話から、あの雪玉の秘密や、竹で雨戸を外す工夫を実践してみせるきりりとした力弥の華々しさなど、
悲しみがありながらも、今際の際に気炎上がる戦の話がなんだか楽しそうで手向けとなり、
男たちの九段目を見たという後味になりました。
これで概ね今年の忠臣蔵大会は終わりですかね。
天河屋が残っちゃった。
チケットはアソビューで500円引きで取りました。
紙のチケットを現地の受付で取りおいてくれています。席はそこでわかる。二階の最前列の中央部。
新国立劇場中劇場の二階は前列の手すりに照明がついており、後半になると熱で陽炎が立ち、舞台上の雪景色がゆらゆら揺れるのを眺めるような感じで、その中で本蔵が討たれていました。
風情といえば風情ですが手すりも視界に入るし、背が高くない勢には二階最前列はお勧めしません。お正月のご参考に。
後から、eプラスの得チケが出ていたので、そっちを試せばよかった。
歌舞伎座|秀山祭九月大歌舞伎|菅原伝授手習鑑
今年の一大プロジェクトであるはずの三大古典通し上演の2つめ。菅原伝授手習鑑の通し上演です。AB昼夜見ました。

ちらちらとは見たことがあるはずですが、如何に何も見てなかったかを思い知りました。
やっぱ、通しは面白いよねえ、っていうのが総じての感想。
いつも寺子屋で姿の見えない不憫な桜丸を思うばかりだったのが、
不幸のスパイラルに陥る前の元の三つ子がどんな人だったのかに想いを馳せたり、源蔵と梅王丸の連携プレーを応援したりしました。面白い話だったんだな。最後ひどいけど。本当に不憫なのは小太郎じゃんね。
今回の通しは仁左衛門から幸四郎への菅丞相の継承にスポットが当たっていますが、滅多にかからない幕が多いため他の役も世代交代が著しく、白太夫や覚寿だってそうなのだと振り返って気づきました。
とにかく、それなりの選抜メンバーで総当たりでやってみよう的な意図を感じます。
この機会に色々な役者にチャレンジしてもらうのはいいですけど、客からするとせめて昼と夜で桜丸から松王丸になるみたいな交換は避けて欲しかった。マジで混ざるので。
ただ、「らしくないけど味がある」反則勝ちみたいなのがちょいちょいあったのは面白く見ました。#主に歌昇
色々言われたけど、実力を見せた染五郎の源蔵には拍手したい。(他の人にも機会を作れという話はまた別の問題としてあるが。)
仁左衛門が終盤、舞台上で体調を崩されたそうで、幸四郎が1日代役。千穐楽は復帰されましたが少しでも休息していただきたいです。
全体通して”まさにその人で賞”は、仁左衛門の菅丞相を別にすると、魁春の覚寿。
姿が好きなのは加茂堤の萬太郎の桜丸。
通しのすごく長いあれこれはこの下に。
昼の部
加茂堤
この話は俳優祭の放送で見たことがあるだけ。たぶん。(自分の記憶が全く当てにならない。)
Aプロを通して見てから文楽の詞章を読みました。
冒頭で休んでいる舎人たちは床本では松王丸、梅王丸で、数奇な生い立ちの説明を梅王丸がしています。歌舞伎の通しでだいぶわけがわかるもののまだふわっとしていたのは、これをよく掴まずに見てたからのようです。(それでもかなり面白かったが。)
三方に分かれた同じ役目の三つ子の話であることが既にいちばんの発明なんだな。
加茂堤 Aプロ
桜丸/歌昇、八重/新悟、齊世親王/米吉、苅屋姫/左近
牛飼い童と呼ばれた人々は大人になっても童形のままだそうで、そのイメージで三つ子ともあんな頭なのかと思いますが(のちに松王が前髪を落とすというのは、その身分を抜け出すということではないか。)桜丸は純粋にあの頭に似つかわしい年齢のイメージがあります。同い年なのに。
でも歌昇は桜丸にしてはだいぶおとなに見えます。なんかの理由でもう似合わない学生服を着て登校してるちょっと先輩の高校生(成人済)みたいな雰囲気がしていて、この感じで情事のことを言われるとだいぶ気恥ずかしいです。
きゃー、ですよ。
新悟の八重も世間のことを心得たお嬢さんに見えます。この人は前に寺子屋の戸浪をやった時にも見事な共犯者でした。頑張って牛を引いて帰るのも、任せといて!って感じ。
で、この二人が帝の弟ぎみと、菅丞相の娘の恋を取り持つという話。
左近はかわいいけれど、姫にしては深窓度が足らないかな。少し「民」な雰囲気があります。
米吉は流石におっとりしている。義太夫が十七歳と言ってて再認識。
時平の家来である三善清行に坂東亀蔵(ABとも)。無理なく似合う。ちょうどいい。
歌昇の桜丸ですが、立ち回りの力強さは案外場に似つかわしい。
ふくらはぎがパンと張っているのが見えて、桜丸強かったんだなと。これはきっと梅王や松王と喧嘩できる強さだもの。
この雄々しき桜丸が後に泣き暮らして憔悴して腹切ってしまうんだと思うとそれはそれでかなしい。
加茂堤 Bプロ
桜丸/萬太郎、八重/種之助、齊世親王/新悟、苅屋姫/米吉
凛々しく若い萬太郎らしい桜丸です。この頭と衣裳がしみじみ似合います。若衆似合う選手権でもかなり上位にいくはず。
色模様のことは何のことかわからないくらいにスルーしていくのでNHKでも安心。お子様を連れてくるならこっち。
亀蔵の三善と対峙すると菊五郎劇団の香りがします。
立ち回りの際に義太夫が「顔に似合わぬ」みたいなことを語ってるのがぴったりの働きぶりで、もう少し立ち回りが続いたらいいのにと思うくらい。
八重も上品、控えめで、もうちょっと八重パート濃くてもいいんじゃないかな。
最後にかかってきてとんぼを返るたった1人の仕丁(ABともやゑ亮らしい)が、八重と左右が合わなかったりして微妙でした。不調な日もあるんだね。
米吉はこちらでは姫です。安定感があります。
新悟の齊世の君はマネキンくらいに視線が定まり微動だにしません。それが動き出して逃げねばならない。大変。
筆法伝授
前の歌舞伎座さよならの時に見たはず。
どんなだっけ?結構話が進んでも全然記憶に引っ掛かりがない。
だが仁左衛門の菅丞相が、「真名といい」と言ったとたん、見たわ間違いなく、と確信しました。
そこしか記憶にない。なのに一丁前に寺子屋の源蔵夫婦がわかりやすくなったみたいなことをメモしている。
何を見てヨシって言ったんですかね私。
また忘れそうなので、筋も交えつつ書いておきます。
筆法伝授 Aプロ
菅丞相/仁左衛門、源蔵/幸四郎、戸浪/時蔵
Aプロは十年前の通しに近い配役です。
菅丞相はそろそろ筆法を誰かに伝えなさいよと朝廷から言われています。(この時点でちょっといぶかしいんですね。)それで七日の潔斎をしており、齊世の君と苅屋姫がいなくなってしまったことを知らされていません。
古参弟子の希世(ABとも橘太郎)は何度清書を提出しても採用されず。腰元にちょっかいを出したりして如何にも清くない感じなのでさもありなん。(史実の平希世は清涼殿の落雷で亡くなっているそうで、それでこんな役どころなのですね。)
局・水無瀬(吉弥)がただ1人取次として菅丞相に信頼されている様には納得感があります。この人なら秘密も漏れず仕事もしっかりでしょう。
そこへ勘当されていた源蔵、戸浪の夫婦が急に呼び出されて来ます。着物は皆売り払ってしまい源蔵の裃は損料もの。
裸足にハッとしました。足袋まで揃えられないんだ。戸浪は昔、園生の前からいただいた小袖を着てきます。
園生の前は雀右衛門。優しい方です。戸浪が自分達の着物のことを言うので見てしまうのですが、秋草を市松模様と組み合わせたシックないい打掛けを着ています。
源蔵だけ菅丞相のいる学問所に立ち入ることを許され、幾つもの襖のある廊下を局水無瀬と歩いていきます。周り舞台を回しながら人も歩いてゆく長い道のりは一面で終わらず、源蔵にとってだいぶ高い敷居だということかもしれません。ふすまを開けると真っ白なお召し物の菅丞相、仁左衛門。気高く。ありがたく拝むばかり。
源蔵は子どもに字を教えて生計を立てている身の上を話し、菅丞相から渡された手本を、希世にいろんな邪魔をされつつ一心不乱に清書し終えます。(ここ、ABとも源蔵は本当に文字を書いている。)そして先に言及した「真名といい、仮名といい」のお褒めをいただいて、めでたく神道秘文伝授の一巻を賜ります、が、勘当は許されない。
菅丞相に必死のお願いをする幸四郎の源蔵はリアル寄りで義太夫の味ではないけれど、仁左衛門と幸四郎という関係性のフィルターを通すと、御浜御殿の時のように染みるものに思えます。
物忌の明けぬうちに急に参内となった菅丞相の冠が落ちる不吉の予感。
後で幸四郎の菅丞相を見てから振り返れば、仁左衛門は作為を全く感じさせなかった。すっと落ちた冠。
早く帰れと言われながら見送る源蔵夫婦。
戸浪の、菅丞相にちゃんと会えなかったこと(御台所の打掛けに隠れてそっと見たのみ)に対する、貴方はいいけど私は…のような結構長めの口説が、時蔵の戸浪はそれを言わなそうなだけに、意外に思われました。
この狂言は、男女差や、身分や、職のあるなしなどから生じる摩擦も他の物語よりも多く語っている気がします。ちょいちょいしんどい台詞があります。
この後、源蔵と希世で一悶着。
(ここ、梅玉で見たい気がする。お仕置きするの良くないですか)
参内した菅丞相は戻った時には罪人扱いとなっていました。帝の態度もまた、技は惜しむ、罪は罪なのだね。
異変を知らせに戻る梅王丸はABとも橋之助。この梅王は好きです。わたくしなく菅丞相に仕えていて、熱血漢できっぱりしています。
梅王丸は役人に手向かいするも、菅丞相から勅定に従うように言われ抗えない。
しかし、もはや菅丞相と主従ではない源蔵夫妻ならその命令は及ばない。源蔵の啖呵に胸がすきます。
幸四郎の源蔵はどこか時代劇みたいですが、尾羽うち枯らした浪人のここぞの働きの実感があります。元は公家に仕えていたという風情は幸四郎にはあまりないかもしれません。
子供の頃から菅丞相に可愛がられていたのはよくわかり、それがそのまま侍になってここに至る気がします。
そして夫婦と梅王丸の連携で、菅丞相の息子菅秀才を密かに救出。梅王丸の仕事も良い。
菅秀才が築地塀の上に現れると、驚きのビジュアル。ちっっさ。菅秀才七つ。AB共に秀乃介。
戸浪が菅秀才を背負い、あの園生の前(=管秀才の母)からいただいた小袖をねんねこにして落ちてゆきます。
そうかそうか。いつも菅秀才いきなりいるけれど、こういうことなのね。
(源蔵は損料ものの袴は着替えてきたんだろうか、その袴で血刀拭って大丈夫か。ちぎった肌着の袖は大丈夫?自分の?って心配になって幕。)
ところで、自分は勘違いしていたのですが、菅丞相は本当に筋を通して源蔵を勘当しており、源蔵は勝手に菅秀才を助け出すので、別に深慮遠謀で勘当継続したわけじゃないのですね。
筆法伝授 Bプロ
菅丞相/幸四郎、源蔵/染五郎、戸浪/壱太郎
橘太郎の希世をあしらう水無瀬は萬次郎。酸いも甘いもという雰囲気がある。加えて園生の前は萬壽という劇団っぽい組み合わせに染五郎の源蔵と壱太郎の戸浪が入ってきます。
親子のニンの違いなのか経験の違いか、染五郎の源蔵には時代劇方向のリアルは感じません。たぶん歌舞伎。あとの寺子屋よりは若い印象があります。
戸浪が小袖以外売ってしまった身の上を話す所はAの時蔵よりも切々とした感情を見せています。壱太郎の特性かと。
そして固唾を飲んで待った幸四郎初役の菅丞相の姿。
そこに菅丞相の拵えの幸四郎がいる、幸四郎の台詞が聞こえるという事実はあって、仁左衛門のような一瞬があるという判断はできても、菅丞相かどうかはわからない。菅丞相の設定年齢五十二歳は実際の幸四郎と近い年齢なのですがそれに説得力があるのかどうかもわからない。誰も菅秀才の顔を知らないのにも似ている。
(だが後に出てくる覚寿は、これは覚寿だと確信できるので、何か一定のラインはあるのかもしれん。)
若干何考えてるかわからない気はします。仁左衛門はそういう得体の知れない感じではないんで、おいおい定まってくるのでしょう。
後半築地塀の所は染五郎がより若い。書生みたいにみえます。息子夫婦の奮闘みたいなイメージ。
壱太郎は男と対峙しても遜色ない働きの戸浪を見せています。護られることを前提としない女子です。戸浪を発見した思いがしました。
(時蔵も勿論同じ働きをしているのだけど、壱太郎ほど夫と同じラインに立っているアピールがない。これがコンビの釣り合いによるのか、個性なのかは源蔵の歳の差が極端すぎてわからない。)
花道で源蔵、戸浪がお互いの手を取っての思い入れが良かった。
道明寺
きっと初見。(昼の演目に見た見てないの差が出るのはなんでや?と思ったが、歌舞伎座さよならのときは、加茂堤と何か、筆法伝授となにか、道明寺と何かっていう組み合わせで三部制で半通しだった。それで真ん中だけ見たのか。)
道明寺 Aプロ
話の具合からシナプス総動員で脳内関係図をなんとか作成しました。
苅屋姫と立田が出て来て母娘だと思ったのに、その後で現れた覚寿が姫のお母さんで、立田にとってもお母さん?ということは姫と立田は姉妹?えー、親子三代にしか見えん。
菅丞相はおばである覚寿の所に立ち寄っている。姫はここから貰われたのか。
覚寿はABとも魁春。会ったことない覚寿なのに覚寿そのものと思ってしまいます。綺麗な白髪でかくしゃくとした厳しい老母です。目の周りにいつもの赤い色をさしていないのですっきりとしている。娘の仇をとったり、重そうな木像を持ち上げて運んだり、間違いなく老いた母なのに、この覚寿様ならやるわなと納得。
立田はキャリアウーマンぽい。ABとも孝太郎。落ち着いたまともな人だが夫運が最悪です。
宿禰太郎/松緑、土師兵衛/歌六。
宿禰太郎は立田の夫。赤っ面に緑と蜜柑色の着物。わるものかぁ。(人を見た目で判断していいのが歌舞伎である。)
つまり立田が家に帰ったらあの太郎がいるんよね。合わんなー。
その父、土師兵衛は息子の出世の為、時平に取り入ろうと菅丞相の暗殺を企てる。鶏受難。
松緑の宿禰太郎は単純におばかさんなのがいい。立田を斬るときも逡巡がない。歌六との組み合わせだと、しょーがねえ息子ができちゃったねってぼやきが聞こえそう。
この話と、菅丞相が彫った自身の木像の不思議と、流罪となる菅丞相と苅屋姫の別れがこの幕。
幕開きからふわぁと香が薫るのが感じられますが、そこに菅丞相(もしくは木像)がいたからかと、上手の一間が開いてわかる。
仁左衛門の菅丞相は木像の所も菅丞相のままでした。
菅丞相を受け取りに来る輝国は菊五郎(8)。清廉。ぴったり。
苅屋姫は加茂堤に引き続き左近。健闘。姫に抱きつかれたり、振り返るほんの一瞬に菅丞相が人に戻る感があります。そのとき姫は気付いていない。哀しみが胸に残る。
道明寺 Bプロ
宿禰太郎が歌昇、土師兵衛が又五郎。親子で親子役。Aよりは翳りのある組み合わせです。
歌昇は太郎を多少の情がある人としてやっているよう。立田に未練があって顔に出している。迷った挙句刺せず、親が無理に介添えして殺す。
でもこの役にその逡巡は邪魔じゃないかしらん。
ひとりでできる段取りではないので、又五郎と相談の上でそうなっているのでしょう。
鶏もちょっとリアル寄りに演技させていた。(そういえばカショーマン、大道芸の人だったわ。)
菅丞相は幸四郎。「実は木像」の菅丞相がごとごとと音がしそうな動きで目で見て面白かった。ここは仁左衛門は僅かに違和感があるかなくらいで、ほぼ菅丞相としてやっていました。幸四郎のは、お客さんにはわかったほうがいいでしょ?って考え方でしょうか。まず違いが出てくるのは少し動きのあるこの幕なのかな。
輝国は錦之助。苅屋姫は米吉。さすがにいじらしいだけでは終わらない情があります。今気付いたけど小川さん多い。
鶏を早く鳴かせる方法といい、木像といい「奇譚」めいていますが、覚寿や姫のドラマがあるためこの幕が残ったのでそれに巻き込まれて残っているんでしょう。
上演されない部分にはまだ荒唐無稽な所があり、それ含めての通しは、国立劇場が戻ってくるときまで待たねばなりませんかね。
仁左衛門の菅丞相を継ぐ以外の視点で、別の選択肢があってもいいでしょう。
ここまで昼の部。
夜の部
車引
ここはいつものやつ。
この話、勝手にどっかに行っちゃう牛が好きです。加茂堤ではあんなに動かなかったのに(あれは親王様の牛)。
やゑ亮が書いていた、車は崩壊しているし、牛はいないし、車をとどろかせよと言われても…という話を思い出してしまいます。牛係は松王丸だよね。牛の性格も似るのかな。
車引 Aプロ
梅王丸/染五郎、桜丸/左近、松王丸/幸四郎
このあいだ見たのは菊之助襲名だったので、まず梅桜のサイズ感が普通なのにほっとしました。ちょうどいい。
二人とも所作に違和感はありませんが、染五郎は無理に声を出しているのがつらい。
あと、杉王丸が廣太郎なんですが、このあいだの小さいくせに仕事きっちりな種太郎杉王と比べてしまうんですよね。
余計な残像がちらつきます。
幸四郎が出てくると安心。釣り合いとしては疑問ですが、三代で出したかったんですね。
時平は白鸚。七月の鬼平の時よりずっと張りがありました。
決して楽ではなく一音一音を腹から絞り出しているのがわかるだけに、ありがたいと思います。
車引 Bプロ
梅王丸/松緑、桜丸/錦之助、松王丸/芝翫
この三人ならこの並びでしょう。
松緑の梅王丸は迫力がある。一度三階で見ましたが、花道を引っ込むのが近くで見たくなり一階の後ろの方をもう一度取ってしまった。この人の今月の三役の中では梅王だなー。
芝翫はこれがあってよかった。もう一役は、道明寺で水に潜る奴さんだもの。(だがあっちのインパクトも強い。)
錦之助桜丸は少し力が弱いかと思うのだけど、若い風情で、言ってることがわかるのは助かります。
今回は桜丸と梅王丸二人の会話が伝わってきました。
これがいつもは案外むずい。なにしろ梅王が何言ってるか分からんもん。
通して発端から見て、桜丸と梅王丸は抱えている事情も違うとわかり、Bプロのここへきて、梅王丸の台詞が何故かわかって、ぴーんと繋がった。
(突然英語が聞こえるとか、訛りがわかる的な聞こえ方だった。)
しばらくぶりに会って、首尾を確かめて、
お互いに賀の祝があるからと思いとどまったことがあるのを伝えて、
そこに時平が通るから、チクショー!とにかくひと言言うんだ!っていう話なんだね。
知ってて待ち構えてたのかと思ってた。
#今まで何を見てヨシって言ってたんですか案件
お?って思ったのが時平、権十郎。なんでもできるからってこの位置に来ちゃうんだという驚き。
メモ 兄弟が様式的にやり合っているところの
ひゃりやりやーりーやーりーやーひゃりやー ひっ
…っていうお囃子、「さらし」というそうですが
それが3回目ですごく速くなるの。
神谷町小歌舞伎でお囃子がすごく速くなるのあったなと思い出した
Aはこんな速くならなかった気がする のだがもう確かめられない
賀の祝
見たことある。いつぶりか思い出せない。前の團十郎が生きていた頃な気がします。親子兄弟訣別の幕。
賀の祝 Aプロ
松王丸/歌昇、梅王丸/橋之助、桜丸/時蔵、千代/新悟、春/種之助、八重/壱太郎、白太夫/又五郎
通し上演で加茂堤と賀の祝の配役シャッフルはよくないと実感しました。
男女ペアがそのままで立場が変わるのがまたよくない。
特にAは、加茂堤で発端を作った歌昇、新悟の桜丸夫婦が松王丸夫婦にチェンジして啖呵を切って家を出てしまう。
全く雰囲気の違う時蔵の桜丸が腹を切り、壱太郎の八重は自分のしたことも覚えてないようで、おろおろしています。
そうだよねえ、あなたじゃないものねと、朝見たものが案外ノイズになってしまう。
そのことは一旦置くとして、
歌昇の松王丸には、持ち前の翳りというか、二面性のようなものが生きているように思います。
明日からは元服して名前も変わるんだ!と突っ張って出て行ってしまいますが、裏腹な内面がありそうで、
オヤジが頭巾をかぶらないなら自分がかぶるという謎のフォローの風情もなんか良いです。その頭巾を後で眺めてね。
要するにへそ曲がりなのね。
梅王丸はここでは喧嘩の相手的な存在ですが、橋之助は菅秀才の件からの繋がりがあるので言葉に説得力が出ます。
時蔵の桜丸は、「桜丸が不憫でござる」のイメージの具現。
この日まではと、生きた屍のように命を繋いできたのでしょう。
もし夜だけ見るならという注釈付きベストの桜丸。
賀の祝 Bプロ
松王丸/彦三郎、梅王丸/萬太郎、桜丸/菊五郎8、千代/新悟、春/種之助、八重/米吉、白太夫/歌六
Bは加茂堤の桜丸夫婦、萬太郎・種之助が梅王丸夫婦になります。萬太郎は梅も桜もどっちもいいが、梅かなー。(でも朝の桜ももう一度見たいな。)
種之助は春の方が合ってる気がします。少し落ち着きがあるほうがよいのかな。萬次郎の表情に少し似てると思いました。
来ない桜丸を待つ米吉の八重はふわっとした不安の予感を感じさせる程度なのがよいです。
今月の全ての中で、彦三郎松王丸と萬太郎梅王丸の喧嘩がいちばん楽しい。
小さめの萬太郎が声も身体も大きい彦三郎に充分拮抗できているのがいい。ちょっと巻き戻して見たい。
(B立師 やゑ亮とのこと)
彦三郎の松王丸はひねていてもその道のりが直線的でカクカク曲がっていくのではというイメージ。
Bの楽では喧嘩の後、珍しく隈取りが滲んでおり、家を出る時にはピエロの泣き顔のように左目の下にツーッと一筋赤い雫が流れていて、芝居は泣いてないのに化粧が泣いておりました。
メモ 時平公のしょたゆう…松王はしょたゆうと読んでましたがたぶん諸大夫(しょだいぶ)では?
とにかくそれになると言ってましたので、
身分は低くとも天神(菅丞相)の使いの牛を想起させる牛飼の世界から出てゆき、それなりの身分をもらう。
印である前髪を剃り落とす。名前も「丸」のついたこどもの名前ではなくなるのですね。
早く出ていけと追い出されるさまは菅丞相から勘当を受けた源蔵と二重写しになります。
神である菅丞相との関わりを断ち、牛車も御殿も霊異もなく、人間がそれぞれできる精一杯を頑張る寺子屋の話に松王丸が入ってくるための儀式が、自ら勘当を受けるということかもしれない、とおもったり。
(この松王播磨守云々の台詞は歌舞伎の入れごとらしく、文楽の本にはありません)
閑話休題
桜丸は菊五郎(8)。加茂堤と繋がる桜丸はこっちかもしれません。少し線が太い。
八重はちょっと止めすぎなくらい止めるのですが、桜丸は揺らがない。(ここは後に改めたのか、回数が減りました)
白太夫はなんとなく歌六の方が良いように思います。虚勢を張って他の息子たちを追い出してからの介錯(首切りではなく、鉦を叩いて往生を助けていると思われる)も乱れに乱れる親心。
寺子屋
時系列的には菅秀才が八歳なので筆法伝授から一年内外の話です。あれから源蔵夫婦の暮らし向きも少し良くなったのかもしれません。源蔵が足袋履いてるし。寺子も沢山いるし。
今回は寺入りの長いバージョンが付きます。
涎くりはABとも男女蔵。机の上に線香持って立たされたり、天秤棒を持った下男三助(吉之丞)と、千代・戸浪のやり取りを真似た場面を繰り広げたりしています。お二人ともなかなか達者。
男女蔵は最近いい感じなことが増えてきました。フェーズが変わった気がしています。
お子様は、菅秀才が秀乃助、小太郎が種太郎の兄弟。
寺子屋 Aプロ
源蔵/幸四郎、松王丸/松緑、戸浪/孝太郎、千代/萬壽、春藤玄蕃/坂東亀蔵、園生の前/東蔵
孝太郎の戸浪が相変わらずのポーカーフェイスで涎くりのお仕置きをしています。源蔵と戸浪が二人三脚で寺子屋を運営しているのが見える。
千代は萬壽。戸浪が多くて千代は珍しいのでは。割合抑えた感じです。
幸四郎と孝太郎のコンビはすわりが良い。
(メモ「いずれを見ても山家育ち」の後は「世話甲斐のない」と言い切る形。
せまじきものは宮仕えじゃなは役者がセリフで言っている。染五郎の源蔵も同じ型。)
それらしい風情の玄蕃が出てきたのには安堵。
お父さんそっくり。そして松王丸となんだかバディー感が漂う。これは珍しいかもしれない。
掛け合いも息ぴったり。
松緑の松王丸は銀鼠の着物。全体的に感情が顔に出て、小太郎が斬られた時の動揺も大きく、底が割れるどころかダダ漏れ。
御免くだされと泣く時も、感情の整理がつかずにずっと泣いています。ここは桜丸のことは口実で小太郎のことで泣いていると見える場合が多いですが、松緑のはこれまでの悔やみがみんな混ざったものがだばだば溢れているように見えます。やりすぎだと思いますが、桜丸の分も泣いてくれているとは思える。
千代が比較的静かなので足して割ったら丁度良い的なアレ。
孝太郎の戸浪はこまごまとかいがいしく立ち働き、色々の段取りをみんな戸浪が揃えているみたいな印象です。筆法伝授の壱太郎も戸浪の働きをくっきりした輪郭に描いていましたので上方の役者さんの捉え方かもしれません。
寺子屋 Bプロ
源蔵/染五郎、松王丸/幸四郎、戸浪/時蔵、千代/雀右衛門、春藤玄蕃/錦吾、園生の前/高麗蔵
染五郎の源蔵は昼の筆法伝授から比べるとぐっと大人で立派。別人に見えます。この幕はよく掛かるのでどう作ったらよいかわかっているのかもしれません。
花道から帰ってくる時の翳が濃く、寺入りした小太郎を見て目を見開いて止まり、明るくなる表情の落差が激しい。
それが何を思ってのことか分かるだけに残酷。
誰がやってもあまり気持ち良くはないですが、源蔵の好感度を落とさないやり方はないものかな。それは欺瞞というものかしら。
源蔵、戸浪のコンビネーションは心地よく仕上がっています。
戸浪は時蔵。
これだけの年齢差でこの釣り合いは予想しませんでした。
昼の染五郎と壱太郎では壱太郎が少し姉さん女房で前に出ているように見えたので、時蔵が抑制しているのかも。
時蔵の戸浪は当然そうだろうという感情の表し方をしますし、全て歌舞伎の女房らしくしみじみとして良いのですが、うっかり見ていると引っかかる所なく過ぎてしまいます。
今回ABの通しを見て、もうちょい強めの個性でよいのかもしれないと思うに至りました。
幸四郎の松王丸は黒い着物。しばらくぶりに黒いのを見て寧ろ新鮮。
菊五郎(8)のどうもニンではない松王や松緑の変わった松王(ごめん)を見た後だと、あ、多分こっちが正解なんと違う?となります。幸四郎のほかの二役(菅丞相と源蔵)に比べても気負いがなく芝居も大きい。
※Bプロ千穐楽にもう一度行ったのですが、「なにとて松のつれなかるらむ」のあたりから張りが減っていて
あれ?このあいだはもう少しきっちりやってなかったっけ?って物足りない気分。代役もあってお疲れかもしれません
玄蕃はちょっと、残念。リズム感がどうも。
雀右衛門の千代は意外にも初役だそう。
机、文庫での応戦の手際がごたごたしますかね。
小太郎の事を話すと悲しみが滲み出て、そうは言っても自然に泣けちゃうという風情が雀右衛門らしく、いいお母さんだなとなってほだされてしまいます。
“松のつれなかるらむ”の歌はどうやって松王丸に届いたのでしょう。菅丞相はそんなつもりじゃなかったでしょうよ。
菅秀才が道明寺の菅丞相そのままに、自分の身代わりになると知っていればという台詞を語りますが、
源蔵も(梅王丸も)、松王丸も、誰にも命じられずにその存在の為に働いて、松王丸夫婦は自らの宝であるこどもを差し出し、源蔵夫婦はその罪は自分に回ってくると知りながら他人の子の命を奪っている。
管秀才がお出ましになれば皆が客に尻を向けて頭を下げます。管秀才本人の意志に関係なく。(歌舞伎では壇上の主人に頭を下げるときでも、向かい合っているつもりという約束で、客席側に向かったままになりますので、主要人物の尻が客席を向く事態はそうありません)
歌舞伎を見始めた頃や沢山の時代劇を見ていた子どもの頃はむしろそいういう価値観はそういうものとして見ることができておりましたが、
いま、特に若い染五郎の源蔵が畳にべったりと這いつくばるさまを見ると、異様だなと思ってしまう。分別あるおとながわかってかしずいているのとは違う盲信の危うさがあるようで。
自分の価値観が時代によって変化したことが主でしょうが、どこかリアルを想起させる高麗屋の色が染五郎にもあるのかもしれません。
いい松王丸ってどんなんでしょうね。色々見たらわからんようになってきました。
元々分かっていたわけでもありませんがおじさま達のそれなりに出来上がっている芝居を見てきたのが、ここで発展途上の寺子屋が立て続けに現れ、はぁ、色んな松がありますねと。源蔵はまだ、この源蔵は分かる、ってこともあるのですが、今日のはよかったなーって松王丸にはまだ巡り会っていない気がします。
そのほかに小劇場1本見ておりますが、2時間半の作品で、2時間半あったらこの倍は物語を進められるぞー、削れ削れそぎ落とせーと思ってみてました。
さて、来月は千本桜。
(20250929 junjun)