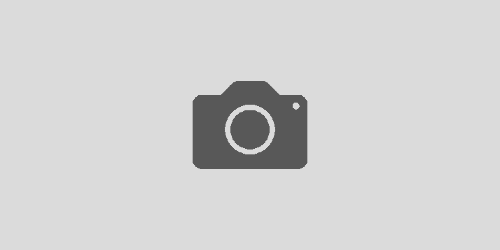2025年10月に観たもの(翔之會、歌舞伎座千本桜、御園座菊五郎襲名、又五郎家巡業、松也ルキなど)

珍しくひと月に2回もミュージカル観ました
オーケストラの演奏会も行ったし、邦楽器も聴いたので音楽の割合が高くなりましたがやっぱりマゲが好き
そしてなぜか道成寺が3回。最後のは予想外。
思い出されるのは断片で、勘九郎の高速毛振り、木の実のご機嫌そうな仁左衛門、いいもん代表彦三郎のお白洲、子どもを抱えた萬太郎保名など。もう一度観たいと思うのは左近小金吾、泥棒と若殿。
仁左衛門は割といつも、ああ、今日もええもん見たなあって感じで、巻き戻したいという感触とは違う。今月はこれでほくほく。でも次も観たい、また観たいっていう感じかな。
だんだん次が望めなくなるのを悟りながら。
[stoc]
もくじ
第十回 翔之會
10/3 浅草公会堂
鷹之資(大ちゃん)の自主公演、第十回
演目は奴道成寺と、浅草祭
なんつー大変そうな組み合わせ
浅草公会堂ですが歌舞伎座の鳳凰丸の揚げ幕が掛かっていました
自分は、かなりの確率で道成寺寝ちゃうのですが、奴道成寺は変わった趣向もあり面白く拝見しました
恋の手習でお化粧する所なんかぐるぐるーっとこないだとうかぶでやってたおてもやんの振りみたい。
お坊さんはくりくり坊主の所化ではなく、狂言に出てきそうな頭巾を被った強力でやり取りもシンプル。蔦之助、精四郎。手拭いも撒いてました。
実質三人の踊りになる所も多く、皆達者でした。
ご当地で見る浅草祭の相方は勘九郎。
大ちゃんは百%以上の、めいっぱいの踊りで、これは自主公演ならではかと思います。
同世代の中ではずば抜けて上手いと思うのですが、勘九郎はまた次元の違う上手さで、胸を借りた感じになっていました。
連獅子も凄かったな
大ちゃんががむしゃらに付いていっているのを
ぶっちぎるようにぎゅんぎゅんと頭を回し始める勘九郎
速度が獅子の毛振りじゃなく、もうフラフープみたいで。
鷹之資は、素手だと非常に重心を身体の軸に引きつけた印象の踊りになり、勘九郎の遠心力を生かす踊りと対照的です
長いものを持つと腕が延びたかのように見栄えがするので
晒しとか毛とか薙刀とかがあるほうが良いのかもしれない
お囃子は歌舞伎座では見ない組み合わせの混成部隊でした。最近、獅子ものだと太左成さんが太鼓のことが多くて、あ、今回もだ、とわくわく。
ところで、十回目でひと区切りとするようなことを、鷹之資さんが以前にトークで言っていたことがあり、最後かなって身構えていたのですが
挨拶でも全然そんなことには触れず
これは十一回目もあるのかな
大長編 タローマン 万博大爆発
タローマンの映画
タローマンは教養溢れるNHKの番組です。(意見には個人差があります)
タローマンって短時間の一発アイデア番組じゃないすか
それをちゃんと長い映画のストーリーにしてきていてあっぱれです
コラージュみたいな感触は減っていますが
ああ、レギュラー陣はこういう人だったのかーって、長尺で初めて見る設定に驚いたりしました
やあ、でも本当に’70年代にこのまとまった質と馬鹿馬鹿しさの作品があったらやっぱ伝説になると思う
ちゃんとミニチュアやブルーバックで撮ってるらしい
あんまり褒めるとタローマンがやる気をなくすのでこっそりにしておきます
渋谷パルコで一緒にやってた展示会も観てきました
川崎市美術館で同じ展示が12月14日まであるそうです
そっちのが広そうでよかったかな
ミュージカル SPY×FAMILY
私の見た回は、ロイド/森崎ウィン、ヨル/唯月ふうか、アーニャ/泉谷星奈、ユーリ/吉高志音
日生劇場はいつぶりだろうか。歌舞伎座が閉まってるとき以来かもしれない。壁の装飾など独特な劇場です。
家族三人とも絵から抜け出てきたみたいだし、ダレることなく進みましたが
え?ここまでなの?まだ何も始まってねぇえぇってとこで終わりました
そしたら2があるそうな。なーるほど。
ヘンダーソン先生役の鈴木壮麻がめっぽう上手かったです。
中井智弥 箏・二十五絃箏リサイタル2025東京公演〜時をこえて〜
10/12 hakujuホール
西洋の音階も出せるお琴、二十五絃箏の演奏家で、刀剣乱舞歌舞伎の音楽を手がけている中井さんのコンサートです
二十五絃箏、十六絃、琵琶、尺八、笛、打ち物と揃って、今年はかなりとうかぶ寄りのラインナップでした
聴きながら、歌昇くんのシーンが浮かびました
(だが最後の方は一作目に戻って松也で上書き)
雪の日の別れがありありと思い出されたり
刀剣男士達のご当地に因んだ踊りの曲もあり
民謡は中井さんの弾き語りでした。歌うんだ。
終演後自分はすぐ出てきちゃったけど
お見送りのおこぼれをいただいて演奏者の方と間近にすれ違ったのも良かったな
サントラ出ませんかね
今度の円盤にはサントラ付いてなさそうなんですよ
出てほしい
歌舞伎座 錦秋十月大歌舞伎 義経千本桜
今年の三大古典上演のみっつめ。
若い世代をそれぞれの主演に据えて、二部だけは仁左衛門と松緑という、ベテランから中堅への橋渡しになりました。
三月から、菊之助(→菊五郎)、勘九郎、松緑、愛之助、幸四郎達が真ん中に立ってきて、今月は少し若い人達が競って。
ここに團十郎が入ってこないのはなんでなんだろう。どこに入れるかと言われると困るけど、若い子があぶれないとこにはめるなら例えば四段目の由良之助と、今月の権太のどっちかは團十郎でも良かったんじゃなかろうか。別に観たいってわけじゃなくて、なんか変だな
今月の話にもどりまして
Aプロは二部のみ、Bプロは全部見ました。
Bプロ一部(鳥居前、渡海屋・大物浦)
鳥居前 Bプロ
忠信/尾上右近、静御前/左近、弁慶/橋之助、義経/歌昇
(とうとう市川右近くんが同月に出るということで、尾上を付けときます。)
破綻のない出来だと思います。滞りなく安定している。
弁慶は橋之助。こういう役アリなんだなと思えてきました。
義経はパッと見で成駒屋兄弟の誰かかと思って、声を聞いたら歌昇でした。あれ?
四天王は、桂三、男寅、玉太郎、吉之丞。
玉太郎は立役の方が所作がいけてるかもしれない。
左近の静御前は義経とのコンビネーションよし。
右近の忠信は荒事の中にスマートさがある忠信。声は張りすぎやも。
橘太郎率いる家来達には安心します。
この人が前にいて立ち回りが怪しいわけがない。
渡海屋 Bプロ
銀平実は知盛/巳之助、お柳実は典侍の局/孝太郎
相模五郎が松緑で、入江丹蔵が坂東亀蔵。A班は逆の組み合わせだそう。
丹蔵の御注進が亀蔵で見られたのは自分としては良し。惚れ惚れするカタチ。かかっている侍はやゑ六だそうです。
孝太郎の御乳の人が立派で本当に良い。
かつてあった王国の存在を証明する最後の人。気丈で気高い。胸にせまります。
大物浦 Bプロ
巳之助の知盛。乾いて荒んだ心の知盛が鋭い怒りを浴びせてきます。
歌昇の義経は、絶対的な尊さの余裕で高みから対峙するのではなく近い高さにいるように思います。
冷ややかに見えて本心は情がある。この辺は静との別れについてもそのように見えました。
義経とて落ちゆく身なのですが安徳帝を肩に抱き、遠く前を見て歩む絶望しない御大将です。
ここに現実的なドラマを感じさせるのが若い人たちの組み合わせで、昨年でしたか、團十郎のひとり千本桜の際に義経代役で松也が入った時、知盛がこんな歳の若い義経に滅ぼされた口惜しさを大きな目で語っているようで、この義経が梅玉だったらそう見えないだろう。義経によって知盛の見え方が変わり得るという気づきがありました。
今回も、帝を預かる義経の在り方により、託した側の最期への向かい方が変わって見えているかもしれません。
最後に橋之助が花道で法螺貝を自分で吹いており
私の見た日はきれいに鳴っていて物語に余韻を残していました。
二部はAプロも見ました
Aプロ二部(木の実、小金吾討死、すし屋)
木の実 Aプロ
権太は松緑、小金吾は新悟、若葉の内侍に魁春
お子様は種太郎、秀乃介兄弟。小せんが種之助
権太、江戸っ子です。
以前の七代目菊五郎はどうだったかとすし屋の録画を見ていたら、年齢もあるでしょうが結構さらっと無愛想にやってました。
松緑はもっと明る目で溌剌な感じ。
私の見た日、善太郎に賽子遊びをさせる所でツボからコロコロと一つはみ出てしまったサイコロに
「うまくいかなかったなもう一回」と促して2回目は成功。
自然なフォローがお父さんだわー
種之助の小せんはまともそう。女房役はいいですね。
はやる小金吾を制する若菜の内侍はぐっと大人です。
小金吾討死 Aプロ
新悟の小金吾は立ち回りに慣れていないとみえて
囃子と斬るタイミングと討手の皆さんのトンボが合いません。トンボが返り終わってから刀が走る感じ。
瀕死で、若君と御台様と柔らかく諭すようにお話する所がようやく彼の持ち味の出た所です。しどころがあると上手いと評した方がありましたが、そうかもしれない。
弥左衛門は橘太郎。刀を振り上げた所に凄みがあり、元は侍だったかのよう。
すし屋 Aプロ
重そうなすし桶を天秤棒で持ち帰ってくる弥助さんはABとも萬壽
花道をトコトコしながら重くて加速度が付いて小走りになってくるのが絶妙
それが維盛卿に「たちまち変わる」のがほんに上手い
こういう、姿は変わらないのに芝居だけで変わる役はなんぼでも見たい
お里は左近。かわいい。
びびびびびのくだりもかわいいけれど、
松緑が復唱するのがかえって可愛かったりする。
あと、寝ましょうの所は短くあっさり。江戸はこんなもん?
台詞的には既に契っているはずですが、左近と萬壽の組み合わせでは何もしてなそうに見えてしまう。
まだ無邪気なお里に大人の維盛が隠していて悪かったと誠実さを見せているという風情でした。
権太がおっかさんを騙して金を出してもらう所は
土瓶のお茶で涙などいつもの松緑のならずもの。
弥左衛門が桶を入れ替えて権太が取り違えるくだりはなし。権太は重さを証拠に持っていく。
弥左衛門女房は齊入。久しぶりに見ました。
権太が持っている笛はAではこの女房が吹きます。
なんだろう、江戸ではすし屋だけの上演が多いからあれが善太郎の笛だという文脈が重視されないのですかね。
Bプロ二部(木の実、小金吾討死、すし屋)
AはAで面白いのですけど、Bプロ二部を見ると、
観客が気づき判断できる、運命の悪戯や、あの時のあれだ!を補助する仕掛けがあり、
また仁左衛門の権太がもっと煽って勢いをつけて転がしていき、没入感というのか、ちょっと客も巻き込まれた感じになっていきます。
木の実 Bプロ
小金吾は左近、若葉の内侍は門之助、子供達は獅童の所のはるちゃんなっちゃん。
権太は言うまでもなく仁左衛門。
荷物を見つけた瞬間から企んでいることがわかる
悪いやつでクズだけれど嫌な男ではない
ああ、企んでる、ああ、ああやっぱりねー、あーあっていう
この感じは江戸だと出ないですね
上方の喜劇です
ここはもう仁左衛門劇場だとわかっているので身を委ねて他のお客さんと一緒に笑うことにする
左近の小金吾は前髪にふさわしい歳の若衆に見えます。
若い子が若い子を演るときのリアルさは、歌舞伎らしくない故に近所の若者みたいに見えるというものが多いですが、
この小金吾は歌舞伎を保ちながら実年齢から出てくるさもありなんという実感がある
性善説で微笑みを浮かべている所に滲む育ちの良さ
年少ゆえの必死さや力及ばずのリアルさ
権太の方が何枚も上手で歯噛みするさまは
仁左衛門の前の左近とぴったり符合します。
そりゃあ敵わないよって言ってあげたいような。
小せんは孝太郎。
この小せんなら来し方もなんとなく納得がいく
権太とのどうでもいいじゃじゃらのしあわせが続かないのを知っているからかなしい。
小金吾討死 Bプロ
左近は、立ち回りの所作を黒御簾の拍子に乗せてきます
とんぼとの連携もよい
百回りが確か2回ありますがそれがまた速い
縄のところは左近も討手の人たちもまだ少し段取りめいていて
できればひと月の日数で進化が見たかった
もっといけるんじゃないかな
若君様、御台様と舞台を彷徨い探すさまの悲壮には蘭平物狂の終盤を思います。
左近ちゃん、かつて、探されていた繁蔵だったのに
「以前に蘭平の『繁蔵はいずれへ参った、ててはここじゃぞ』の所で二代目松緑は自分の鼻を指し、いまの松緑は胸に手を当てていると読んだことがある。
自分を指すときに鼻を指す日本のしぐさは遠くなりつつあるのだろう。
左近の小金吾も掌で胸を叩いている。蘭平はいつか見られるかなとよぎった。」Twitterから
最後、独りになり、あれは偽り、と告白する小金吾は儚さと悲しさで涙を誘うのですが
“実は中身は姫でした”でもおかしくない風情。
それは左近のいいとこでもあり、微妙なとこでもあります。
立役と女形を兼ねているというよりは、未分化で使い分けができてない。そのことがきっと今だけのいとしいないまぜを生んでいるものと思います。
大切に見ておかなければ。いつか蘭平に育っちゃうかもしれないんだから。
すし屋 Bプロ
桶の並べ替えがあったり善太郎の笛を自分で吹く仁左衛門のやり方での上演です
似非涙の水は、バラン(たぶん)を刺した花瓶から取ります
お里は米吉。これは左近よりは年の長けた娘に見えます。この役自体にも慣れている様子。簪が江戸とは違うそう。
弥左衛門女房は梅花。間違いのないおっかさんです。
芝翫の梶原は以前見ていますが、
悪そうで良さそうなちょうどいい所に落としていて、いいですね
仁左衛門の肌ぬぎの姿には年輪を思います。それでもまだ今回権太が見られるというのがありがたい。
また、片脚を水平に上げた「面ぁ上げろ」ではなく、両手を使った型になりました。だからちょっと母子の配置が離れてるのね。(延若の方だそうです。)
仁左衛門の豊かな表現を見てしまうと他の型は語らなすぎると思ってしまう
でも仁左衛門だからできるものなんだよねえ
Bプロ三部(吉野山、四の切)
佐藤忠信・狐忠信/尾上右近、静御前/米吉、逸見藤太/種之助、義経/梅玉
吉野山 Bプロ
吉野山の忠信は行儀の良い踊り。
ただ戦物語の所はもっと役者らしい踊りでも良いと思います。力比べの所など面白く見たいもの。
私が見た日は逸見藤太の笠ブーメランキャッチも片足だちも問題なく成功。
静御前を見送った後、周囲を見上げて見回しながらの引っ込みは右近らしさを感じさせます
いちめんのさくらだー、ほらー、お客さんも感じてーって言いたいんだろうなあ
そこまでの抑えたテイストから現代的な写実の感覚になっているように見えます
NHKの特別番組だったら見回した所にCGでぽぽぽって桜が咲くんじゃないかっていう雰囲気でした
川連法眼館 Bプロ
歌女之丞の飛鳥が良い。
本物忠信はきっちり。
狐になってからケンケンらしさが出ます。
詞の通りに、子どもの頃に親と別れて、大人になったけれど、親孝行できなかったことがずっと気掛かりな青年というキャラクターになっています。
狐言葉は右近独特な気がするんよな。
静御前はアクセントが東京になる所があり気になりました。(これは、鳥居前左近も。)
義経公は梅玉。うん、鼓をあげよう、って決めるところが実に偉い人の思考に見えて良い。若い子だとこうはなりませんね。
2階ロビーには義経千本桜をイメージした生け花がありました。数日ごとに変えていたそう。
あと、いままで(ここしばらく?)無かった気がするのですが
開演前の場内アナウンスに松竹歌舞伎会の宣伝が入ってました。
創立60周年記念 都響スペシャル「すぎやまこういちの交響宇宙」
東京芸術劇場コンサートホール
曲目解説などこちら
https://www.tmso.or.jp/j/concert/detail/detail.php?id=3940
カンタータ・オルビスと交響曲イデオンを含む全曲演奏会初演のコンサートです。
シャボン玉の弾けるような風情の「日本の風」が好きでした
自分は、イデオン、さすがだな、厚いいい演奏だなって思ったけど、この解釈じゃないと思われた方もあったようです。
客層はイデオンリアルタイム勢が結構いたんじゃないかな
上の階のバルコニー席から眺めると下の客席がよく見えますが
皆が拍手している最中にスマホで写真撮ってた人がいました。
これはフォトセッションのあるアニソン系オーケストラ演奏会の悪しき影響ではなかろうか
御園座 第五十一回吉例顔見世
歌舞伎で御園座に来るのは久しぶりかも
建て替え後、ほかの演劇では来たことあるんですが、少なくとも、幕間に客席でごはんを食べた覚えがありません
いまは、幕間は電波遮断なし
席でお弁当食べられる(昔はダメだった)
最中アイスも本当に久しぶり。ぱりっぱりで美味い
客層は、頭が黒い人が多い。以前はもっとおばあちゃんがいたと思う。
席は10列目が取れました
歌舞伎座より傾斜があり見やすいです。
それと花道の際の席は大変花道に近い。
その際の席の一人一人の着席時に花道に物を置くなと係の人が言いにきて大変な気配り。
いい感じに置きたくなる高さなのは浅草と似てるかな。
ナレーションはひと通りあり。
まだマスク推奨と言ってました。
また「ここで、同時解説イヤホンガイドの…」ってもはや歌舞伎座では流れないナレーションを聞きました。
イヤホンの所だけイヤホンガイドの人が喋るんだね
襲名祝幕は富士山
各劇場のサイズで同じ絵を使って幕にしてるのですね
右下の提供者の名前も歌舞伎座とは違いました
昼の部(操り三番叟、葛の葉、二人道成寺)
操り三番叟
三番叟は長唄バージョンのようです。
千歳/吉弥、翁/錦之助
三番叟の人形は鷹之資。
吉太朗が後見で、まずはご挨拶。おおさえおーさえ喜びありや…の歌もあり。お人形は足を鳴らせないので、ダンッて踏んであげるのも役目。面白いよねー。
もう1人いる付け後見は音蔵。
鷹之資は踊っている最中はそこまでかっちり人形っぽくやっていないですが、パタンとなってるときの息はぴったり。きっかけの声や足拍子もなく糸に吊られる腕がすごいですよね。伏せているのに拍だけで合わせているってこと?
近くの席の方が、”良かった。だいぶ習った(練習したの意味)のね。”とおっしゃってました。
芦屋道満大内鑑 葛の葉
葛の葉/時蔵、保名/萬太郎
時蔵の葛の葉は安定
当たり役ですね。
いま舞台裏で急いでる筈、出るぞ出るぞとわかってるのに、あれ?機の音してるよね?って思ってしまう
彌紋さんのお嬢さんが童子で出ていたらしいですが私の見た日がそうだったかどうかは分からず。
童子さんは狐の葛の葉に転がされてぱたんぱたんと寝返りするのが見事でした
萬ちゃん保名はかわいい
たぶん本来はテイストが違うんだろうな
でもこれもありかなと思わせる
御幣を取って陰陽師として真実を見極めようとする凛とした所も、女房が狐でも恥ずかしくないときっぱり言うところも、今の感覚で見て、いい旦那です。この人の優しさの見える役は良い。
葛の葉の曲書きの障子の道具を倒すと芒と菊の野原が現れ
叢に付いて義太夫も出てくる(草木にカモフラージュして近づいてくるやつみたいだw)
うっすら見せながらの転換が面白い
力者が二人と狐の戦い
これはなんで戦ってるんだ?
元々が凄く長い話で、何がどうなってるやらわけわかめなのでいったいどの段階の何が追ってきたのかわかりませんが、保名か本物の葛の葉の敵なんでしょうね
狐葛の葉かっこいいなという所で幕
京鹿子娘二人道成寺
二人の白拍子を八代目菊五郎と、六代目菊之助の親子で。
新菊之助が、歌舞伎座では中に大人が入って真面目に動かしてるみたいな感じだったのが年齢なりのかわいさが出てきました
少し微笑んで踊るようにしたのかな
以前は笠に振り回されていた所にも余裕が出ました。
鞠のところも一人で。
強くなったのう
恋の話は八代目で、女子の成長過程を分担してるのだね。
そして、寝てしま…今日は寝ないと思ったのにな。
まいづくしは鷹之資
よどみなくこなし、龍角散まで準備していました
***余談
眼鏡のせいか歳のせいか同じくらいの座席位置でも他の劇場では見づらいのですが
御園座の照明は舞台の人のコントラストがくっきりしてよく見えるようです
何が違うんだろう
明るいのかな?
そう思って見ると貼り紙とかお手洗いの中の表示とか
すべてがはっきり書かれている
余白があんまりなかったりするのでちょっとくどいのですが、
係の人も先回りするので考える前に誘導されてしまう
(なおほぼ全部日本人向け。外国人が殆どいない)
***
夜の部(羽衣、口上、鼠小僧)
新古演劇十種の内 羽衣
天女/雀右衛門、伯竜/錦之助
配役の妙。
家の宝にしよう、国の宝にしようと空気読まない漁師と、困っている女性がいつもの世話もののに見えちゃって。
あと、大道具の松が割合大味でほのぼの。
舞の装束になってからは流石に天人に戻られます。
雲の向こうに斜めに上がっていくような大道具になってました。
八代目尾上菊五郎 六代目尾上菊之助 襲名披露 口上
主要な俳優さんが揃った形で、東京では口上に出なかった方の言葉が聞けました。
披露は雀右衛門から。
うわぁ、雀右衛門がその位置にきちゃったのか。年月が恐ろしい。そこには先代がいらしたのに。
床についた手が震えていました。毎日どきどきでしょうね。
片岡亀蔵は御園座十何年ぶりだとか。
錦之助が前売り買ってねの宣伝。
口上に出たことがないらしい萬太郎は、東京での梅王丸の指導を担当したことに触れていました。
後列お弟子さんが9人。1人足らない。
菊三呂がけんけんとこに付いてるのか。
萬次郎も時蔵も立役の裃でしたので、女形の拵えは雀右衛門と梅之助だけでした。
鼠小紋春着雛形 鼠小僧次郎吉
導入に黙阿弥の弟子として菊次が出てきて庚申の夜の話をしてくれます。
自分の隣の席の人たちが、幕間で寺嶋しのぶの父は何代目なの?初代じゃない?っていうびっくり会話をしていたので、本当に菊次さんの師匠が黙阿弥だと思ってないか心配になってしまった。流石に大丈夫かな。
主人公の稲葉幸蔵(鼠小僧)は八代目菊五郎。
こういう役は七代目にそっくりになってきました。
化粧もですが、脚の筋肉が似てる。
七代目の姿から八代目の声が出てるみたいで、戸惑います。
配役はこの芝居を30年ぶりに復活させた3年前とはだいぶ変わっていますが
菊五郎劇団らしく、それぞれはまり役に当てていて良いです。
特にごうつく婆さんのおくま(萬次郎)がいい。
ひとつ、菊市郎と菊史郎がおんなじ顔なので
お金が盗まれた時嫌なやつにバチが当たったのかなと思って観てたらどうも話が違う。
辻番(亀蔵)の話を聞きながら、
あ、もしかして、さっきの宿直の侍は菊史郎だわ。悪いほうが菊市郎だなって頭で整理してました。
気の毒な刀屋新助に萬太郎。恋人のお元に芝のぶ。
この気の毒配置も萬太郎の持ちポジション。
困ったような顔しながら幸蔵の帰りをずっと待ってたんだなと想像。
その後、次から次へと因縁のあるひとが、主人公のもとを訪れる。どんどん引き寄せるんだね。
菊之助のしじみ売りの子は、子役の台詞という感じでなく、お芝居になってきました。
文七元結のお久ができる年齢に近づいてきましたね。
お嬢様行方不明の所は少し唐突で、カットされた所があるのかも。
かどわかしの場面は本当はあるのかしら。
お嬢様おみつに吉太朗、惚れられる若者与之助に鷹之資。今月ずっとコンビ。
松山(時蔵)の見えない目がなんで見えたのか疑問に思ってる方がおられましたが、
歌詞で鳥目だと言ってるので、夜目は利かないけど、明るくなれば見えるということ。
鐘は鳴っている、幸蔵が早く名乗り出ないとあの辻番のおとっつぁんのお裁きが下ってしまう。
でも生き別れた女房との再会と別れもしなくっちゃ。気がもめるー。
(鼠小僧氏は大きい声で色々明かしちゃう癖があるのがいけないと思うの。)
全ての埒をあけて自主した鼠小僧のお裁き担当の早瀬なにがしは彦三郎。いかにもいい方の侍。
この芝居でいちばん気分がいいのは、お裁きのついた後、慈悲のある裁きには従うが無理に縛れば縄を抜けて逃げるというギアチェンジ
これがなくてお裁きで終わってしまったら誠につまらない
「取り逃したか」とうそぶく早瀬に礼を言って消えていく
時代ものの、さらばさらばと別れゆくラストを世話にしたような、鼠小僧のヒロイズムを感じるかっこいい幕切れでした
ミュージカル エリザベート
シアターオーブ
私の見た日は
エリザベート/明日海りお、トート/井上芳雄、フランツ/佐藤隆紀、ルドルフ/中桐聖弥、ゾフィー/香寿たつき、ルキーニ/尾上松也
初エリザです。
前日に御園座で菊五郎劇団の流れを汲むひととおりの芝居を観て、ここに松也がいる未来もあったかもしれないねって感傷がなかったと言ったら嘘になります。
でもエリザベートでこの位置に立てる未来ならこっちの方がいいのかなあ。
そしてルキーニのさまざまな所業は、やぁ、松也だなーと思って拝見しました。
自由と評してる方も多いようです。(みんなミルク運搬の人が東北弁て言ってるけど北関東くらいだと思う。いや、それはどうでもいいが)
芝居と思って見ればそこまでの逸脱に見えないけど、他の人はやらないってことかな。
ミュージカルだから歌があってなんぼですが、この役は語りと仕事も多くて、講談師、見てきたようななんとやら、という感じです。
松也はこういう語り手の役割は上手い。
でも、内側から噴出するような感情の見える役こそ、っても思う。
井上芳雄さんは後半になるほど幅の広い深い声で、すごいスケール。
明日海りおさんはアルトの音域の曲のほうが魅力あるなと思いました。1曲だけあって、それがいいなー。
で、自分この話好きかどうかっていうと
いやぁ?
主人公に思い入れられない大河ドラマという感じでしょうか。
来月もう一回観る予定。
松竹大歌舞伎(巡業)
公文協の巡業
初日が藤沢で、10月の最後の最後からのスタート。
最近、巡業だと解説パートが入ったミニ版みたいなのもありますが、今回は芝居と踊りの二本立てで解説のない”大歌舞伎”の巡業です。
泥棒と若殿
泥棒が歌昇、種之助が若殿。もう配役を見ただけで勝利でしょう?
歌昇はまず太腿が太い。(おい)
最初がどたばたしすぎで、そんなにずっとびくついていなくても良さそうですが。
あと酔って寝ちゃうタイプに見えない。実は起きてそう。でも世話焼きなにいちゃんという関係性はしっくり。洗い物しながら随分歌ってましたが、歌も好きなのかな。
七歳のときからしじみ売りや、ただのノブで忠信のセリフには今月の他の芝居を思わずにはいられず。
実は兄弟共に若殿がニンなのではと思いますが、もし歌昇だとちょっと重いかもしれない。
種之助は繊細であってもぴりぴりと尖った殿様ではなく、小さな動物が必死で身を守っていたような日々が思われ、
周囲が皆承知の上であれこれ仕組んでいたことを知った情けなさや悲しみが真に迫っていました。
また周五郎らしい語りが種之助は上手い。
これは歌舞伎の入れごとかもしれませんが、伝九の元からみんな逃げていくと指摘するセリフが最後に思い出されます。
自分も去ることを伝える所にはまだ説得力が出るのではないか。
幕切れはやはり花道のある劇場で観たいと思いました。(たぶん周り舞台じゃないのに装置が回るのにはちょっとびっくり。道具側が回るのかな。)
歌昇はこういうとこでしっかり泣くし、泣かせます。
初日を見る限りでは若殿の側の物語に見えます。
松緑と巳之助のを観た時は泥棒の側の物語のように見えたけれど、今日のは、客に聞かせ考えさせるパートを種之助が担っている感じでした。
梅から桜へ季節が巡るまでのわずかな日々、また観たいな。
お祭り
浅葱幕が落ちる前に背景画の上手の端がチラッと見えて、象がいるんですよ。象??ってなってたら、さまざまな山車が描かれていました。
又五郎と歌昇は鳶頭、種之助は芸者。
お祭りはしょっちゅう上演があるので、だいぶ構成は覚えてきましたが、途中に道成寺が混ざってて、は?ってなりました。
どんな道成寺かは観てのお楽しみ。
歌昇の袖からチラッと見える彫り物がハッとさせます。やっぱ白塗り似合うな。さっきまで泥棒だったのに。
若すぎる若い者こと子どもたちが二人で踊る時には、お兄ちゃんがぐっと低くなって弟に合わせていました
うたたね兄弟もそうやってきたんだろうなあって思いを馳せてしまった
思ったより体格差があります
木の実のときにはそんなに差があるとおもわなかったな。
あとは運動会もあります
鳶頭のことを「正義の味方みたいだよね」と近くの席の方が話してました。

藤沢市民会館は来年三月で一旦閉館し建て直しの予定
緞帳がエモエモでございますよ
松下電器の下に見える以前の表記の痕跡がナショナルカラーテレビですもん
ナショナルが白物、パナがオーディオ等と分化する前
それも、カタカナでNのないナショナルロゴ付き
昭和四十年代の開館当初のものでしょう
いすゞのほうも何か書いてあった痕がありましたが読めないな。
翌日は山形公演。一気に飛びますね
また近くを通ったときに行くつもりです
(20251101 junjun)