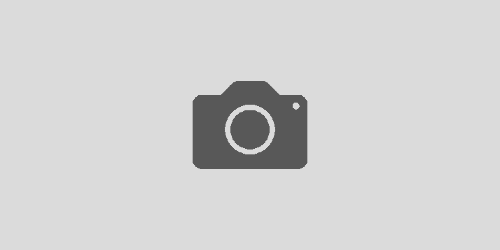2025年6月に見たもの(ザ・カブキ、歌舞伎座菊五郎襲名など)

「6月に見て印象深きもの
・歌舞伎座芝浜の飲み会(なんとか家話にしか見えない)
・暫という無形の何かを背負う成田屋
・小さい杉王
・歌舞伎家話5周年。小道具の関さん(ナマ!)
・少女仮面で渦巻く紙吹雪を背負って出る松也と共に移動する扇風機
・正しく忠臣蔵なバレエ
・土屋主税という演目自体」
以上X(Twitter)から
都度都度書いてたら常体敬体(だ・である、ですます)がごちゃごちゃです。ごめん。
[stoc]
もくじ
歌舞伎座
5月に引き続き、菊五郎、菊之助の襲名公演
昼
元禄花見踊
明治に書かれたそうだが、曲が面白い。お馴染みの冒頭フレーズは琴のよう。途中完全に洋楽のコード進行になっているところもあるのに楽器は三味線。話題になったろうな。
右近が阿国、隼人が山左。
阿国の方は男の格好をしている女を男が演じるというややこしいことになっており、少し男まさりでやはり兼ねる人という雰囲気。
途中元禄の男の一人の左近との絡みでは、左近に色気があり、これが男の色気ではないのでまたややこしい。(いいんだけどここで出すのは違うよ)
車引
梅王丸に新菊之助が挑む。
役が決まってからの長い準備期間、萬太郎がお稽古をみていたそうで、なるほどの楷書。音羽屋的にはなかなか回って来ないだろう役だけれど、この子は似合いそう。だけど喉を枯らしていてかわいそうだった。そのため台詞の意味は取れず。
2回見たが2回目の方が出せる声域を掴んでいた。
今回、弟桜丸の方が大きくて、吉太朗。
もう少し柔らかみがあってもいいかな。それと二人とももっと大きな振りでもいいと思う。
松王丸は鷹之資。梅王をやってほしい所だけど松王も良い。皆が言及する足の親指がまたすごい。
そしてまじまじ見てしまったのが種太郎の杉王丸。いちばん小さい。一丁前に(と言いたくなる体格差)梅桜兄弟に相対峙し、松王の補助など自分の役目もちゃんと果たし、動かぬところではしっかり体勢をキープ。幕切れでも四番目の兄弟みたいに極まっていた。面白いじゃん。歌昇マンのお子は二人ともやるなあ。
子どもたちに出番を作っていくのも八代目菊五郎の意図かもしれない。
寺子屋
菊五郎8と愛之助で2回目の寺子屋。
前回松王丸はニンに合わないし、鬘も大き過ぎるし、低い作り声を無理に出していて厳しいと思った。
今回はそこまで無理をしておらず、源蔵夫婦と向き合っての身の上話に心情が見えた。これが最近半年くらいの八代目菊五郎のテイスト。俊寛の時に感じたのと同じものだ。義太夫らしくはないと思う。新歌舞伎みたいな印象が残る。
あ、鬘も変えたと思う。そうしたら今度は松王らしくないような。難しい。
戸浪は雀右衛門。前回の新悟は鮮やかに夫の共犯者になったが、雀右衛門は慎みがある。それが愛之助の源蔵をも慎ましく見せているのではないか。源蔵は前回の何か企んでいる人の風情に対しこの演目の筋通りの悩む人に見えた。
今回は寺入りからで、千代は時蔵、いうことなし。
涎くりと玄蕃の舞台写真が出ていて絵が面白くて買った。
涎くりは精四郎。大きい。
玄蕃が萬太郎。前よりも鋭く作っていて良くなったが、この位置が定着するのは違うよねえ。それこそ精四郎にこの役が回るといいのに。今月は大小逆転が多いな。
寺子としては「子ども歌舞伎スクール寺子屋」の子達も出ていて、小道具のお習字もスクールの子達が書いたそうだ。
菅秀才は昨年(元の)菊之助が寺子屋をやったときと同じ子役さんらしい。女の子かと思ったら男の子でした。だいぶ色々に出てるので将来もしや?と思ってしまうが、どうかな。
お祭り
仁左衛門のお祭り
まってましたがかからない。掛けないでねと決めているのかな。芸者は孝太郎。安定の組み合わせ。
対して珍しい組み合わせなのが鳶の者。彦亀兄弟が獅子舞の前脚、隼人、歌之助が後脚で、坂東亀蔵と歌之助は年齢ダブルスコアだそう。しっかり支えてくれた若者ありがとう。
手古舞に壱太郎、種之助、米吉、児太郎。種之助を見てしまう。
清元の立唄が栄寿太夫すなわち尾上右近。地の声は低めで慎重に音をとっているように思う。高音にも無理に絞り出すような聞きづらさがないのは良かった。清元としてどうなのかは自分にはわからない。
夜
暫
荒事って上方歌舞伎よりも絶滅危惧種な気もする。他が荒事をやらなくなっても團十郎だけはやらなきゃいけない。大きな怪物のようなこどもでいる義務がある。暫という無形の何者かを成田屋は背負っている。その重さを感じてしまった。
昔の歌舞伎は一日中このテンポだったんだろうか?いつまでもお祭りを見ているような、観劇というよりは見物な気分。段取通りの儀式をああ次はこれだっけ?と眺める。
腹出し筆頭の男女蔵がなぜか常に斜めなのが気になる
雀右衛門の照葉は初役とのことだが古風な良い味。朝見た出雲阿国はこういう雰囲気でも良いかも。
口上
口上も2ヶ月目となればさらさらしたものだ。
ニザさまだけが毎日隣の松緑をハラハラさせていた模様。
そういえば以前、田之助さんが高齢の幹部の隣で毎日横から助け船を出していると漏らしていた。懐かしい。
全景の舞台写真が出ていたので購入した。お弟子さんが全員並ぶのはなかなかないことなので。
連獅子
菊五郎8、菊之助親子獅子。安定性が高い。なんの心配もなく見られた。
暫があって連獅子があって、これほど歌舞伎らしい見てほしい並びもないと思うのに、なぜか帰ってしまう人がいる。事情はおありでしょうが勿体無い。
芝浜
最後におとなの世話物。前回出たのがわずか3年前。自分はこういった菊五郎(七代目)の世話物が本当に好きだったと再確認した。
今月は主人公の政五郎に松緑。劇団の雰囲気はあるものの非なる芝浜になった。松緑の政五郎は菊五郎7よりもピュアなのかも。
今回、話がどうこうよりも仲良し呑み会がメインかもしれない。彦三郎、亀蔵の兄弟が毎日焼き豆腐と蛤を持ってきてるのだと思うと楽しい。
いつまで同じ話をしてるんだよw 長いよ。紀尾井町家話かよ。
この飲み仲間たちが何年か後にそれぞれきりっとした姿で自分のやるべきことをこなしているのがまた良い。
時蔵が女房役。夫に嘘をついている苛責が胸を責めるというそぶりが、客席に笑いを誘いながらも泣かせる。いい女房だよ。
借金取りのおばさんが橘太郎。これはかなり良い。
なんとかならんかと思うことがひとつ。
この演目は江戸の世話物でなく、落語を元にした新しめの演目で、暗転中に鳴物がない。
暗くて静かでなかなかチョンと鳴らず待たされる。これは変えちゃだめなんですかね。
何か鳴っててもよくない?
で東京襲名興行はお開き。
少女仮面(オフィス3○○ ザ・スズナリ)
唐十郎追悼と銘打って、渡辺えり主演での少女仮面。渡辺えりはかつて主人公の春日野(宝塚の伝説的男役スター)を二十代で演じたのだそう。年齢的には今のほうがリアルに伝わることもあると思われる。老いてゆくことや、自らのイメージを自ら制御できずに仮面のほうが本人に成り代わって独り歩きしていくこと、そしてそれに群がる者たちによって奪われるもの。こういったことは普遍的なテーマだ。
けれど背景に残る戦中、戦後、高度成長期のあれこれは、迷い込んできた少女に春日野の思いが容易に伝わらないのと同じように、いまや伝わらないかもしれないと思う。
私がこの芝居になんで行ったかというと、松也が日替わりゲストで出ていたため。
日替わりゲストさんたちがやるのは、主人公が戦中の慰問先である満州に病気の為取り残されていた時に憧れていたと思われる甘粕大尉の役で、古いデザインの軍服を纏い、寒さ厳しき満州を思わせる紙吹雪と共に後方の入口から入ってきて、紙吹雪を飛ばす扇風機を引き連れて舞台までやってくる。少女漫画ですがな。
(別の日に出ている竹中直人や中村獅童は映像で甘粕大尉を演じたことがあるようだ。うーん。共通項があるようなないような??)
完売後に席を増やしたそうで舞台のごく近くまでお客を入れていた。少しずつ禁じられた事項が解けていく。3年前なら紙吹雪に扇風機だってダメだったろうし、コーヒー(水だけど)をこぼすのもダメだったろう。唐十郎的なものはやはり密でなんぼな気がする。
スズナリ、外観がすごいよね。

歌舞伎鑑賞教室(荒川)
歌舞伎のみかた
解説は青虎。忠臣蔵を知らないと土屋主税はわからないので、忠臣蔵の解説を、「○○のスマホ」風の画面を交えてやってました。
昨年の7月の解説が宗之助で、当月は青虎、7月は坂東亀蔵と、ベテラン勢が続いている。若手よりも人前で話すこと自体に慣れていて聴きやすい。
土屋主税
これは初見。鴈治郎家の演目。
吉良さんのお隣の話で、つまり松浦の太鼓とシチュエーションが同じ話なのだけれど少しずつ違う。
松浦の太鼓はお殿様が勝手に怒っているが、土屋主税では其角(橘三郎)の許へ暇乞いに来た大高源吾(錦之助)が他へ仕官するためだと嘘の理由を述べたため、二君に仕えるとはどういうことなのか、とそこに来てた若干潔癖なお客(其月 (青虎))が怒り出すというきっかけがある。其角も何かひっかかっている。
だが南部坂で大石内蔵助が決して真意を漏らさずに耐えたのと同様、源吾もぐっと耐えて、例の「明日またるるその宝船」の句を詠んで別れる。
ここで思わぬ災難に遭うのは、源吾ではなく勝田新左衛門の妹のお園(新悟)。
ここは松浦の太鼓では大高源吾の妹ということになっている。
土屋主税ではワンクッションあるんですね。源吾がよそへ仕官するのであれば討ち入りはないのだろう、そんな腰抜けの浅野家の浪士の妹を其角は土屋主税に世話してしまった。ちょうど雪が積もって殿様の句会に招かれているので其月と一緒に出かけて、そこで暇をとらせて欲しいともちかけることになる。
殿様土屋主税は扇雀。話をひととおり聞いて「あしたまたるる」の句を解釈しようとするが、外野がうるさくて出来ない(笑)。其角と其月はSNSで勝手に怒って盛り上がってる人たちみたいになっている。
事情を裏で聴いてしまい自害しようとするお園。しかし殿様は討ち入りはあると推理し、案の定。
ことが始まると気になる其角は隣が見たくて木に登っちゃう。
説明に1名当家へ差し向けられるのは源吾だろうと思ってると、源吾が来る。ここ何年か見ていないようなかっこいい錦之助が拝めました。この役は良い。
討ち入りに兄も加わっていたと聞いてうれし涙にくれるお園ちゃんにはもらい泣きしそうになった。
そして、先ほどは知らずに無礼を言ったと今度は其月が切腹しようとする。だいぶ起伏の激しい人だな(苦笑)。
怒る役を其月という別の人に当てて、殿様は思慮深い役にしたかったのかな。いつ討ち入るんだろうとイライラして侍女を遠ざけるというのはちょっと無理があるけど、源吾が士官するという明確なきっかけがあって話が動くのは理にかなっている。
アナザー松浦の太鼓として、良いものを見た。東京ではあまり上演がないそう。
そういえば、アソビューというアプリで割引価格でチケットが取れたので使ってみた。係の人も慣れていないようだったが、入口でアソビューで予約しましたと伝えて名前を言うと、取り置きしてくれていたチケットを渡してくれるしくみ。7月は夏休みだからか売り切れていたが、6月は空いていた。たぶんそれ用に空けてあったのかもしれないが私の席の周りは左右3個ずつくらい空いてた。下手の前から5列目で簡易花道が見やすいところだった。
発券作業がないのは楽。もっと知られると良いな。
あと、EG-Gというアプリで字幕が無料で見られるというので、それも使ってみた。(まえに稚魚の会かなんかで入れていたのですぐ使えた。)
会場の電光掲示板には義太夫の詞は出るが、黒御簾の中の唄の詞は出ない。でもアプリの字幕にはそれも出ている。役者さんを見ている最中にはアプリを見る暇がないけど舞踊のときの補助には良いのでは。
歌舞伎家話5周年特別企画 「裏表夢戯場仕掛(たねあかしかぶきのからくり)~小道具編~」(幸四郎・壱太郎)
プリンスホテルに付属のClub eXというイベントスペースの現地に行きました。
歌舞伎座のアナウンスがへんてこなもの(考えた人ごめん)になってしまったので、ここで聞く「いわいくん」の普通の松竹風アナウンスに、あーー落ち着くと思ったりしました。
真ん中に丸いステージがあり、花道がついていて、客席は円形ステージをぐるっと取り囲むように配置されています。
円形ステージの中には地味に回り舞台もついている。
演者の方は花道を背にして立っていました。(落ち着かぬw。歌舞伎関連のイベントのときだけ、花道方向に向いて立つのはどうでしょうか?。)
なかなか面白そうな会場です。
いくつか小道具がステージに置かれており、開演前と終演後は撮影可能でした。
家話のルールなので例によって話の内容は書かずにおきますが
ちゃんと進行しようとする壱太郎さんを振り切って絶好調の幸四郎さんが相変わらずでした。
役者さんは舞台を見たことがあるけど小道具の関さんは初めてナマで見たー
幸四郎さんは思いつきでだいぶ無茶なものを作らせているようです。
次のイベント企画案も出ていました。家で話すしかなかった時期から5年。次の5年は全然違ったものになるかもしれませんね。
時代考証最前線
べらぼうの時代考証の山村竜也さんと、劇団☆新感線の「座付き作家」中島かずきさんのトークイベント。進行は脚本家の會川昇さん。
書店のイベントなので、山村さんの新刊が出たタイミングで実施の運びとなったようです。配信もありましたが現地に行きました。
最近の大河ドラマは、なんとか考証、なんとか考証…というのがいっぱいあって、今や大河の時代考証はそこから溢れた所や取りまとめみたいな役らしいです。
山村さんは元は新選組専門だったそうで、それがこっちもできませんか?みたいな形で頼まれていくうちに江戸時代ですらないものまで広がってしまったのだそう。
新選組について言うと、隊服が青だったり、あの長い紐(襷にするやつ)が付いてるのは間違いだそう。でも現場はあるものを使いたいからなかなか直らないという事情があるようです。
(あの紐はどっから来たんだろうと思って、栗塚旭の血風録を眺めてみたけど、普通の羽織の紐だったな。)
色の件は浅葱色というからいけないんだ、もう水色と呼べと仰ってましたが、水色というからには浅葱幕みたいな薄い浅葱なんですかね。
(近年染物屋さんが復元した羽織は、写真で見る限りは濃いめに見えます。浅葱色は写真だと伝わらんよね。浅葱も縹も一緒に見える。)
會川さんからは名和弓雄さんのお名前が何度か出てました。
名和さんは私らの世代の時代劇オタクには有名な時代考証家だと思う。
奉行所や武家屋敷に表札があるのはおかしい、捕り方の提灯の文字は側面、小さい燗徳利はあの時代はない…というような突っ込みをし続けた方。
その結果なのかNHKのリメイク系時代劇でも昔と同じ脚本なのに捕り方の服装が違ったり、徳利じゃなくなってるのを私も見てます。
それで、ついにというかなんというか、大岡越前の高橋版2シリーズ(いまのやつ)から時代考証が入ってるんですって。山村さんがご担当。
すごくない?加藤剛時代のフォーマットをそのまま受け継いでC.A.Lが作ってNHKが流している大岡越前に時代考証がはいる。まあ大岡越前はギリあり得るかもしれん。暴れん坊将軍や水戸黄門だったら存在自体と衝突する。
自分は昭和のテレビ時代劇の世界をそのままでやるのもありだと思うんですよ。昭和の技術とフォーマットでやっています。考証的に変なとこもあるけど初演のを尊重してますってテロップ出してやることもできそうじゃん。けどそれは守るべき伝統とは認めらなかったってことかなあ。
みんなの憩いの場である小料理屋(たぬき)は、昭和的に由緒正しい、椅子とテーブルのある間違った飲食店なんですけど、それを変えるのは「ご勘弁を」と言われたそうです。まあそうだろうな。
で、人相書には本当は似顔絵が入っていないそうですが、せめてあの現代っぽい顔の絵じゃなくて浮世絵風の全身像とかはどうか?と言ってるけどそうしてくれないそうで、結局人相書を出さないことになったと。
あれ?人相書って歌舞伎はどういうんだったかな?と手もとにあった引窓の録画を見てみましたら、まさに浮世絵風の全身像が書いてありました。
元々絵がないのが考証的に正しいのであれば、歌舞伎にいつの頃からか絵姿入りの人相書が混入したってことですよね。いつからなんだろう。
なお、中島さんは、実際のどの時代のことでもないということにして考証入れてないそう(そりゃあそうよな)。
東京バレエ団 ザ・カブキ(新国立劇場オペラパレス)
宮川新大さんが由良之助の日に見ました。
忠臣蔵を見たばかりの年にこれが目に入ってきたのでチケット取りましたが、バレエ全く知りません。
ベジャールのザ・カブキという作品があるというのは知ってますが、文字としてである。
いつも歌舞伎が初めての方の新鮮な感想から活力を得たりするので私も初心者中の初心者として書き残しておきます。
パンフも買わずに自力鑑賞という蛮勇をふるいました。
従いまして誰がどれを踊ったのかは分かりません。ごめん。
席はバルコニー。これは自分には良かった気がする。全体が把握できた。
足が地面につかない(バーに乗せる)のはちょっと怖かったけど。
周りの感想を見る限りではよい公演だったよう。知らなすぎてそれを判断することもできなかった。
しかし何やってるかは8割わかる。役もわかる。
ものの本には現代の創作バレエ的に書かれていたので(私が学生の頃はホンマの新作であったろうし)もっと前衛的、抽象的なものかと思ったが、仮名手本を踏まえれば相当具象的に感じる。あんまり忠臣蔵どおりに進むので驚いちゃった。
自分にはバレエの教養はなく、筋のない所はわからない。
例えば由良之助ひとりの踊りは、ストーリー中この位置にあるのだから多分出陣前の意気であろう、みたいな理解をするしかない。
でもそういう所は少なく、殆どはどれがどの役でなんの場面かはっきりわかった。
FFX歌舞伎ですごいすごい原作通りだったって判で押したような感想がよくあったが、あれはこういう気分かと思う
他はわからないから知ってることに頼るとそうなるんだな。
大道具の薮が人間であったり、所々黒衣後見がいたり、人形振り(遣い手付き)とかちょっと目を引くところがあったけれど、ディテールは忘れてしまい
凛とした顔世、おかっぱのかわいいおかる、統率力のありそうな由良之助、そういった印象が残っている
**
最初は大勢で忙しき現代の描写
モニターの映像も交えた表現になっている
初演の時の表現はこんなにキーボードを打つ人がいたのだろうか、それとも文字を書いてたのかな?
このうちの1人がカッターシャツにネクタイで忠臣蔵に紛れ込んでしまうということのようだ。
「頃は暦応元年如月下旬」と大音声が流れる
え?、義太夫? てゆうかここから?
確かにあらすじに書いてあったが、ほんまに大序からやるんかーい、である
傘を差しかけられているのは足利の直義だろう
黒いのが師直かな
顔世と、兜をずらりと並べた兜あらため。
一方、着物のおかる勘平と’80sっぽい男女。
おかると勘平の状況は(当時の)現代で言うとこういうことだよと二重写しにしてくれているのだろう。80年代当時’50sのリバイバルが流行っていたのでそのようにも見える。
今という間に今は過ぎる。やがて新派のように”当時の風俗”に見えるようになり、世話物のように一括りの昔になるのかもしれない。
グラデーションひよこみたいな色の人は鷺坂伴内やな。狂言まわし的にずっと出ている。
松の間刃傷に至るがここは本来大星は出ないんでまだ絡むことができないのだな
勘平は懸命に門を叩いている。「裏門」だ。
で、ロール背景を使っておかると勘平は富士山の見える所までたどり着いた。今は裏門が出ずに五段目の前に所作事の「落人」が入ることが多いが、本来は裏門の続きで二人は落ち延びているはずでこの位置なのだろう。ちゃんとしてるなー。
訪れる2人の人物(赤と黒で元の衣裳とは全く違うが東洋の官吏のイメージ)
白い四角な敷物の四隅に緑の葉の付いた枝が生けられている
四段目とわかる
であれば、由良之助はここに向かっているはずだ
歌舞伎では客に見えない鳥屋の中から足音をさせて花道を駆け込んでくる。
バレエでは走って、所々大股で飛んでくる。これがすごく急いでる表現なのかな。
判官の最期に回り込んで向かって右にくる。(ここは歌舞伎だと左。) おお、由良之助が大ショックを受けているぞ。当事者になった。
その後、一味するかしないかの評定、ある者は残りある者は去り、ずらりと並んだ浪士が次々と連判する。
ここで主人公の青年は明確に由良之助に「成った」。
五、六段目は、おかるが親に頼み込み、与一兵衛が一文字屋で算段をつけ、定九郎が出て、猪(歌舞伎よりややもふもふだが、仕組みはあのまま)が出て二つ玉から、お財布掠奪、おかるの家で中略、財布が見つかり以下略勘平切腹までフルコースある。それが一画面の中ですごくコンパクトに連続で詰め詰めになっていて見事だ。
倒れ伏した勘平をどこからか出現した由良之助が起こして血判させる。
ここで連判状が出るはずと思ったら出る。
この安心感。
物理を気にせず、連判状に加わるのが概念でわかればよいわけで便利だ。
いちばんぼやっとしてたのは七段目かな
実は全編義太夫には相当助けられたが特に印象的だったのはここ。おねえさんが踊ってる。廓だな。どこまで進んだんだろう?って迷子になってたら。
「山科からは(略)鯉口チャンと響かせれば」
(この説明があってから由良之助が寝た気がする)
あ?力弥来る? まだそんな段階か。
きたー。じゃあこれが力弥。
というわけでそこで現在位置を把握。
鷺坂伴内はここでは九太夫の役割を担っていて刺されてしまう。これはよかろ。
おかるが手紙を読んでいたのに気づいて身請けの相談、じゃらじゃらでおかるどうなったんだろう
平右衛門がいないのでちゃんと由良之助がおかるの心底に気付いたか心配だー
次は読めない。
顔世がいるらしい。持った枝の桜は散っている。(これは四段目では花が付いていた。時は移った。)
なぜか赤フンの人たちが横並びになっている。顔世の護りだろうか?
くるくると巻き物になって(おしくらまんじゅうの状態が近い)舞台後方に消える
連判状に連なってるのは人間なんだよということかと思った
上記のふんどしの方々だけではなんの場面かわからないが、編笠姿の侍が来た。顔世の所に来たのだから本蔵ではない。由良之助だ。ということは南部坂だ。あれ?混ざってきたな。
南部坂雪の別れは仮名手本にはない
主人公である大星と顔世との流れを再び結ぶには、加古川本蔵の物語でなくこれが必要なのだろう。
七段目も密書が既に手元にある体でもできそうだがちゃんと力弥がくる。これも顔世と由良之助を繋いでおく意識のように思う。
顔世は由良之助の真意を知らないから怒るはずだ。
亡君の御恩を忘れたか、と指差す先に
白い正方形の敷物。鷹の羽の紋。再び現れる顔なき主君の切腹の場。短刀を大星が受けて、討ち入りの為の集結となる
(忠臣蔵の九寸五分は柄が無く紙を巻きつけて使うが、バレエでは白木の柄が付いている。)
白い浪士たちの群舞
なにしろ頭の引き出しから出てくるのは達陀くらいで
ああ、こうなるべきなんだな達陀、ってちょっと理解した気がする。
このくらいきっぱり揃えば美しいだろう。
太鼓があって、襖を開けて師直を探し
本懐を遂げる
由良之助は師直の首級を示しながら通っていき
並ぶ浪士達はぴょんこぴょんこしている
仇の首を見ての反応だから多分喜んでいる表現なんだろう。陽気だな。
最終的に奥の底辺九人から手前の頂点由良之助までの真っ白な人々の逆三角形を舞台上に形作り正座して切腹して終わり
締めが潔い。
カーテンコールの拍手が鳴り止まず、トリプル以上だったのではないか。
下の階は見えないがこの感じだとスタンディングオベーションになっているのかも
面白かった。忠臣蔵のエッセンスを取り入れたとかじゃなく忠臣蔵そのものを作ったのだな。
他に、小劇場作品の上映1本、知り合いのライブ1本。
7月に向けて買い控えようと思ったのに、結果的にバラエティに富む6月でした。