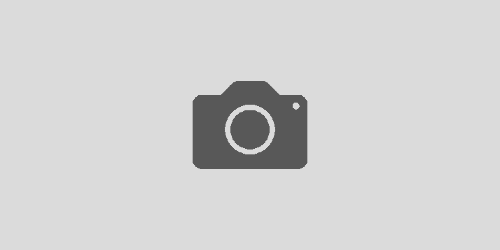弁天小僧と年下の南郷 (少年は変わりゆく 八代目菊五郎襲名&松也 2025.5 歌舞伎座)

弁天小僧が近くでかかるときは誰のでもなるべく観るようにしている。
今月は八代目菊五郎の襲名で本家本元のお家芸。
後日も見るのだけどまずは三階から観てきた。
1回目
見あらわしになった弁天小僧が話していると侍や女方のときとは違う声がする。
おやじさん(七代目)の声(元がきれいすぎるのでつぶしたそうだ)とも違う声。
ティーダの声だ、と思った。
これが八代目の弁天小僧か。
この人の弁天では個性をいちばん強く感じた。
菊之助時代の弁天小僧も見ている。前はもっと七代目を写したような感じだった気がする。
今回は発声もそうだが台詞回しや間など七代目とは違うなと思う所があった。
お店の品を見るときは、最初のは1つめを選ぶ、帯地は見比べて2つめを選ぶ。先を急ぐまではいってないが決断の早いお嬢様に見える。
緋鹿の子は、知らなければ全くわからないくらいに、見えないように取り出している。
ちょっと分からな過ぎないか?と思うくらい。
前はもう少し見えるようにやってたな。
「えっ なんで私を男とはえ。」のところは、第一声から女の声。桜の彫り物に言及されたときはあまり大きく発声しない。(ここは弁天を見るたびメモしている。最近男の声の人はいないよう。)
「おれがことだ」はだいふ大袈裟めに言っている。
色んなお客様が来る月だからわかりやすくかしら。
南郷は松也。先に弁天を経験しているから相棒のやることはわかってるだろう。
(なんなら弁天の台詞も言っちゃう(そういう演出かなと思わせるくらい自然に続けてたが、そんなん他で見たことないのでうっかりだと思う。次の時確認しよ。))
最初から立派なお侍の風情はよい。キセル遣いは吉右衛門くらいのコンパクトさ。
松也らしいのは、百両なれば了見いたそうの素早さ。「よ か ろ う ぜ」で指をくるくるっと回す。このくるくるは独特だなあ。
「はやくしてくんな」のユニゾンなど、待ってましたとばかりに気持ちよさそうにやるコンビもあるが、頑張って頑張ってばちっと合わせてきたのが見えるとかえって野暮じゃないですか。
この二人はさらっと合わせる。それがいい。
逆に言うと客に見せるようにゆっくりとやってみせる所が少ない。
もうちょっと欲しくないですか。
このままいくのか、千穐楽までに変わるのか。楽しみ。
さて。松也南郷で気付かされたことがある。
今日の立ち前の所で「胸に手ぇ当ててかんげぇてみろ」と南郷が言う。
あれ?と思った。
ここは最近、胸に手を当ててぐっと下におろして考えてみろ、というのが多かった気がする。
左團次は確かそういう感じ。
しかし、以前はその、胸に手を当てておろして、のほうに違和感があったような気がする。
昔誰かので「胸に手を当てて」だけで刷り込まれたんだ。誰の南郷だろ。
映像あるかな。VHSの録画…は見れないや。(諸事情)手っ取り早くは古いDVDか。ごそごそ。
そうしたら一発で引き当てた。松竹が出してるやつ。S61年。初代辰之助の南郷だ。
他の場面も見てみる。痛くて痛くての辺りからイロのできねえツラしてやがる、のところの間の詰まったところがおんなじ。これだこれ。
この間だと弁天の覚えてろよ、の台詞がよく聞こえないんでもうちょっと待った方がいいんじゃね?ってところまで同じ。
八代目菊五郎で、イントネーションが違うと思った所も、昔の七代目と同じだった。七代目の方が後年変わったのか。
自分が見た映像は、七代目が44、辰之助が40になる年のものだ。今の八代目の年齢と年下の南郷の取り合わせを見ると、もしかするとわざわざこの頃の浜松屋にしてみたのかもしれない。(ここまで映像)
駄右衛門は團十郎、番頭は橘太郎、若旦那は萬太郎。この人は困り顔が似合う。浜松屋幸兵衛は歌六。鳶頭松緑。この役好きそう。1人もハズレがない座組だと思う。
蔵前の場はナシ。
稲瀬川は新菊之助をはじめとするこども世代。
“どん尻”から上手に向かって、眞秀、梅枝、亀三郎、菊之助、新之助。
皆よくできている。名乗りの最後のフレーズに移る前にほんの少しスピードを緩めるのがそれぞれうまかった。小さい梅枝がふらふらする傘を懸命に支えながら、間の難しい赤星の名乗りをこなしていた。
テレビで見たとき菊之助が気にしていた懐手がうまくいかない所も私の見た日はなんとかできていた。
屋根の上の立ち回りからは大人に戻る。
橘太郎、玉雪などかつての名手が出ている。八大、咲十郎あたりは私も顔がわかる。大和、辰巳…と、もういない面々を思い出す。お客さんそれぞれに懐かしい顔があるだろう。いま若い人で見分けられるのは三人くらいだなあ。着地音のしないとんぼに、これだよねーってなる。それにしても捕り手大渋滞だな。
寺島しのぶが言及していたので橘太郎が屋根に上がることは知っていたが、1回は単独でかかっての返り落ち、もう一度は数人揃っての返り落ちと2回落ちていた。すごい。
この演目を掛けて立ち回りの技を繋いでいくのもまた菊五郎の役割だよね。
ところで、三階Bだと屋根のいちばん上に行ったときの弁天は死角で全く見えないです。あはは。
立ち腹の後がんどう返しで弁天が消えてゆくと
代わって山門になり團十郎の駄右衛門。
さらにせり上がって滑川。土橋に乗って(???)青砥藤綱が出てくる。七代目菊五郎。
そこへさっき消えた八代目が早替わりで伊皿子七郎として出てくる。早っ。
今回は家来1人だけ。
そして七代目、座ったままかと思ったら立った。わーい。(←ほんとに贔屓ってちょろいですね。)
さらばさらばーで幕
あとはなにかあれば足していきます。
(2025.5.6 観劇)
追加1
松緑の鳶頭はカラッとやろうとしているのか、かなり軽い。これだと松也との釣り合いが悪い気がする。
松也南郷は、茶ぁ一杯くれ、が毎回詰まりすぎる。そんなに急がなくていいのに。
どいつもこいつもは、どいつも、こいつも、になってきた。そこだけ左團次っぽさがある。ほかは割と吉右衛門っぽい。
あ、それと前に見たとき「べらぼうに長え返事だな」を自分で言っちゃってましたが、やはりとちりだったようで、後から見た時はちゃんと弁天が言ってましたw
弁天は、「きかせやしょう」も「俺がことだ」もだいぶ時代にやっていて全体的にこの名乗りの所はかなりたっぷり。
相当昔だが、多分巡業で、当時の菊之助がいつもと違う弁天小僧だったことがあった。ここの語りになにがしかのストーリーを盛り込もうという気配が感じられた。
今回だんだんそれに近づいてきた気がしなくもない
個人的には普通に七五七五でやっていいんですよ?と思うけど
花道を二人で歩くと足首の太さの差がわかる。松也は骨が太いね。昔見た七代目菊五郎は足首がきゅっとしたダンサーの脚で、鶏ももみたいだったな。八代目はそこまで筋肉じゃないけど細い。
新菊之助がテレビ番組で傘の向きについて、志ら浪志ら浪ってならなきゃいけない、と向きが決まっていることを語っていた。
菊之助、眞秀は流石に気をつけていてあるべき向きに揃っていた。梅枝はもう、持てているだけでえらい。
(5/10 , 5/12 幕見)
追加2
速報。良くなってた。南郷余裕が出た。もう一度観てから何か書く。
カンカンの稲瀬川日本駄右衛門、「人に情けを掛川から金谷を…」と呼吸を置かずに続けている。毎回そうなのでそれで覚えていると思う。変じゃない?
(5/17)
追加3 ギンビス?
小ネタメモ:
- 南郷は膝に三里あてをしているがいつのまにかないんだよね。
お嬢様が袋叩きになったあと南郷が向き直るときにはない。ここで取ってるのか。いま知った。いかに南郷に注目することがなかったかだよ。
南郷をよく見てると、弁天が何かを始めたら南郷が煙草を詰め始めるみたいな段取りが見える。 - 浜松屋で、倅宗之助(萬太郎)が緋鹿子のきれを確認しようと手を伸ばしながら傍に流されていってしまう様子が癖になるよさ。心配して、やるだけのことはやろうとしたのに非力な、育ちの良い若旦那感。何もせずにおろおろしている若旦那も多いなか。育ちなんだもんね、まさに。
- 今回の子役さんは「おはーい」の止めがちょい早い。それでも特大おはーーーーいーーーのところはだいぶ長くなった。えらい。
- 松緑の鳶頭。万引きするとは気が付かねえの前は「人柄づくりのお嬢さんが」と言っていた。メモ。
(ここは、鳶頭によってバリエーションがある。振り袖姿の、とか、文金島田のとか) - 弁天。「これをわっちらにくださる」は1回。
- 山門の駄右衛門の煙草盆が豪華。團十郎は幕切れで真ん中で口を大きく開けて目をカッと見開いたまま幕が閉まるまで静止している。これだけは他の追随を許さない技術だと思う。ものすごい。
松也の南郷は安定してきた。カッコいい南郷路線。
だが「余のことなれば了見いたす。が。」の「が」をわざとらしく離す。「百両ならば了見いたそう」は、「了見いたそう」で世話な口調になり、金をそそくさとしまう。このあたりだけ小者臭を出しているようだ。男女蔵が男寅だった頃と、あともう一人、こういうやりかたを見たことがある。
玉島逸当の「しかと左様か」の後は「ハテ、くどい事を」と受ける。ハテを結構はっきり言っている。
いいなと思ったのは、弁天が二十両をつき返したときに潮時とみて寄っていって止める所。南郷が考えて主導しているように見える。
その後の「よ か ろ う ぜ」は茶番ぽいが、そこに至るアルゴリズムは世話で良い。
八代目菊五郎の弁天は、さぁさぁさぁの後で顔を上げるとき
以前はもっと眉を動かしてやっていた気がする。最近の七代目がそうしていて、それが私のよく知っている弁天。
もっと昔の七代目の映像は、キッとした顔のまま前を見据えるようにしていて、これが今月の八代目のやり方と似ている。
知らねえのか?のところは少し面白そうな顔をしている。自己紹介のツラネ全体がたっぷり気味なのは今月を通して変わっていない。
最初のころ、そこ以外は全体的にお客にアピールせずにさらさらやっていたが、南郷が弁天の傷を見て大げさにこいつはひでぇやと言う辺りは、先週見たときには、だいぶ声高になっていた。その後の「イロのできねえツラしてやがる」と「覚えてろよ」のタイミングがかぶらなくなった。良い良い。
で。何がギンビスかというと。
花道で南郷から何か忘れ物はないかと問われて、なにもありゃあしねえよ?、そんなことはねえはずのいつものやりとりの中で、なんだろう忘れ物?などと長めにあれこれ考えていた弁天がふと気づいたように
弁天「…ギンビス?」急にぶっ込んできたよ
南郷「…おめえ頭がおかしくなっちまったんじゃねえのか」←本当にそう思ってるに違いないw
弁天「赤ぇキレは持ってきたし…」なおも考える弁天。ちょっと笑い気味で進行せざるを得ない2人
坊主持ちの後で揚幕に引っ込む間際の2人は飲みに行こう等の雑談をしているが、この日は、ギンビスってなんだ?そういうお菓子があるんだよといった話になってた。
なんだろう、なんでギンビス?ww ギンビスの人でも来てたのか、本番の舞台のどこかで特定のワードを言うミッションでもあったのか。
この前に見たときもまだ、忘れ物はないか、なにも忘れ物はないよ、胸に手を当てて考えてみろくらいで、
定番の「赤いきれは持ってきたし」のくだりもなく、すっきりとしてたので、1週間で随分くだけて自分達のものになってきた様子。
昔、巡業で松助さんが南郷、当時の菊之助(今の八代目菊五郎)が弁天だったときに1回、弁天のほうが分け前が多かったていで演じた日があったが、松助南郷は悔しいリアクションができず、少々分け前が少なくても気にしない兄貴になってた。(他の日に見たら普通の進行だったので突然の入れ込みだったのだろう)
子の松也君で、翻弄される南郷がまた見られて嬉しいよ。
(5/25)
おまけ。古い弁天の記憶↓