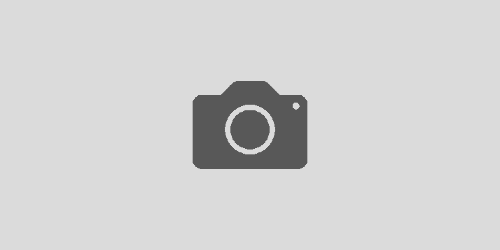2025年7月にみたもの(鬼平、とうかぶ2など)

7月はスケジュール的にやらかしまして
ハシゴできるだろうと思って、歌舞伎座昼、新橋夜で取ったんですよ
そしたら歌舞伎座の終演 16:07、新橋の開演 16:00
よもやよもやだ
で、どうしたかと言うと、紅葉狩を断念
他にもスケジュール的にやらかしがあって鑑賞教室が見られず
ポンコツすぎる。反省。
今月特に考えたのは
お客が持ってる知識をどこまで当たり前とするのか
その踏み台なしでどこまで楽しめるかというようなことです。
あ、ネタバレがあります。
いつもはさほど気にしませんが
翌月以降も続く作品があるのでそこは自衛をお願いします
[stoc]
歌舞伎座昼
新歌舞伎十八番であまりかからないものを交えて。
大森彦七
見たことない演目。そもそも大森彦七という人物を知らない。だが簡単じゃないのに割とわかる。
大森彦七は右團次。
千早姫は児太郎から配役変更にて廣松。大森彦七に父を討たれたと信じ仇討ちを志す姫だ。父は楠木正成。
大森彦七のライバルポジションの道後左衛門は九團次。
道後左衛門が不在のうちにお姫様の身バレ。彦七から楠公最期の物語があって、形見の刀は姫にわたる。刀が奪われたのは楠公の霊のせいということにしておくからこの猿楽の衣裳を着て行きなさいよと。
姫は鬼の面をかけ楠木正成の怨霊として名乗りながら花道を引っ込む。
ここで姫でありながら楠公の霊が降りたかと思えるくらいの入り混じった迫力が出たらきっと良いだろう。萬壽が時蔵だった頃の嫗山姥が思い出された。あんな感じかな。
廣松はまだ若い。全てを失っても再び立つ姫のイメージになった。
そしてその後は大森彦七が大真面目に芝居と踊りで誤魔化しまくる。右團次適役かも。道後左衛門は困惑していて気の毒。何を見せられているのかとはこのことだったろう。
船弁慶
前シテ静御前、團十郎。弁慶は右團次、義経が虎之介。
個人的に前半睡魔がくる演目なのだが今回は寝なかった。
小柄な弁慶が意見して、帰りなさいって言われた大きな静がしょぼんとした表情になっている。御曹司義経は最近困ったイケメン役が来がちな虎之介で、それにこの静がついて来ちゃってる図式がもう面白い。前半に物語を感じたことがあまりなかったので、船弁慶ってそういう話かと思ってみたら少し面白かった。
船頭に梅玉。松緑がよく船弁慶なら船頭の役がやりたいと言うのだけど、なるほど、疲れるほどではなく気持ちもよさそうな役だ。
後シテ知盛の霊は、團十郎ならもっと大きく恐ろしくなりそうだが、決まるところが決まらずスケールが小さい。合う役なのにな。
高時
黙阿弥作とは知らなかった。
お犬様から始まる。既に暴君の予感。
高時は巳之助。僧形なので隠居後のこと。
上手の柱にもたれ掛かり酒を飲みながら。これが古典にはないスタイルだそうだ。言われてみればそうか。当時何が新しかったか、同じ視点で見るのは難しいな。
前半はやむを得ず犬を斬った侍(忖度なき輩に福之助は配役良し)を、死罪にしようとする横暴な高時。後半はなぜか烏天狗(だいぶ大勢)が舞い込んで、田楽舞の一座と思い込んだ高時が指南を頼み翻弄される、アクロバティックな天狗舞の場面。(巳之助は自分でとんぼを返る。)
岡崎の猫と同じようなテイストだった。
前半と後半の繋ぎに酷い殿様だからバチが当たった的な説明は一切なく、出来事どうしにわざわざ因果関係を示さないのが新時代のクールさのような気もする。
面白いかというと、謎。
紅葉狩は私のチョンボで見られず。
歌舞伎座夜
戸部さんトーク
今回の鬼平犯科帳の脚本の戸部和久さんトーク付きの回があったのでまずそれに行きました。
録音、写真OK、SNSへは節度ある投稿をとのこと
録音OKって珍しくない?
節度を客に委ねるとこ、歌舞伎らしいです
まあ「ここだけの話」はされてないのだなという解釈をしておきます。
戸部さん、お正月あたりは自分は関係ないと思ってたんですって。そしたら春頃に脚本書くことになったそうで、ははは。
それで時代劇専門チャンネルに入って延々と吉右衛門版を見たと。
そのキャラクターらしい言い回しが書くときに自然に出てくるようになるまで叩き込まないといけないそうで、
だから、すっごくご覧になって書いてらっしゃるんですね。
それは一部にとても発揮されていて冒頭など、「いつの世も悪は絶えない」ってナレーションが入りそうですもんね。
今回は時代劇を作っているつもりだと。だから音楽もあんな感じ。
時代劇だけど歌舞伎なところもある。
染五郎さんパートは
血で運命を決められることに反発する若き鬼平を
高麗屋に生まれたこの年頃の染五郎さんがやるという
その重なりを意識して書かれたようです
もう一つ
少女の頃のおまさちゃん(市川ぼたん)
この是非についてはお客さんに委ねるそうです
(私の意見は、このような時代劇であれば、座頭の裁量でどうなとしていただければよいが、育ったら新悟ちゃんになりそうな10歳に見える子がよりよかった、です。)
話題の映画について少し言及がありました
実際の歌舞伎では一回やって終わりではなく
お客さんが入って回を重ねながらひと月続いていく
1回であり、23分の1回なのだ
そこを描いてくれたら…(略(節度))
本日の見どころは皆さん自身が観客となることである、とか。
(高次の話になってきたぞ)
…というような話を踏まえて見る鬼平です。
鬼平犯科帳
2回見ました
新作の常としてあとで見たほうが出来が良い
冒頭、黒装束の数人が引き込みの手引きで押し込み、蔵の所で仕事にかかろうかとする
すげー。時代劇だー。テレビの絵じゃん。
呼び子の音、塀の外から火盗の高張り提灯が次々と掲げられ「火付盗賊改方長谷川平蔵である!」と幸四郎の鬼平が踏み出してきます。引き込みは平蔵の手の者彦十、中には火盗改の皆さんが待ち伏せしていたのだー。
この「長谷川平蔵である」の「である」。現行の時専版幸四郎鬼平は「である」を言いません。ということは、幸四郎が演ってるけど吉右衛門の鬼平なんですよ。(早口のヲタク)
すげーなあほんとにテレビ版やるんだなーって見てたら
盗賊のカシラの成田屋が出てきて、立ち回りなどあり、神妙に縛について
成田屋ァ!って展開があり、
ぉ、おぅ。歌舞伎になるんだここ、という。
ところが新手が現れ新たなバトルが発生だ。
回る盆を駆け抜けつつ、今の鬼平からシームレスに若き日の鬼平に移行する。
このダイナミックさと説明のなさ。
映像ならどんな感じか想像できますね。
まあ面白いからいいか。
前回道具ぐるぐるをやっていた刀剣乱舞が今回は回るところを見せるのをやめちゃったので、江戸の仇を長崎方式で楽しませていただきました。
平蔵の若い頃の銕三郎を演じるのは、最近の映画と同様染五郎。
遊んでいた頃のてっつぁんは割とえげつない。
染五郎の表現は江戸っ子っぽいとこはあるけれど荒削りで
リアルな若さからくる無鉄砲味に支配されている
木挽町のあだ討ちのときもそうだった
もし時が過ぎこれに頼れなくなった時、ここはどんな表現になるのだろう
夜鷹のおもんの話は原作の後日鬼平になってからの話からの輸入。夜鷹でも人として分け隔てなく扱う所は若い頃からだよと言いたかったのかな。
昭和の太秦的(これは松竹もふくめ)な、時代考証的になにも正しくなく、時代劇的に正しい居酒屋が出てきて笑いました。テーブル、燗徳利、縄のれんの三拍子揃っている。
五鉄のほうは流石に座敷。先代の主人役寿猿さん。元気でなにより。ここはいいシーン。
悪者夫婦の宗之助、猿弥もすごく良いけどすぐやられて勿体なすぎる。
この辺ちょっと面白くなってきたと思った所で、ナウシカの”殺してから王蟲は泣くんだわ”的な事態が生じる。
だいぶ力技で、わかるだろー! わからないわよおにいちゃんのバカバカバカ的な展開になります(ほぼネタバレ)。
おまさのこども時代はあまり原作にも書いてないので創作だと思いますが、
おまさも銕っつぁんも説明を放棄していて、流石にわからない。
お守りをもらった銕のポエムの後、夜空にスモークの高麗屋ファンタジーに、こちらが宇宙猫みたいな顔になって幕間。
裏表太閤記も空海も晴明も許すけど鬼平にそれはどうよ
幕間の後は「血闘」の話になります。
大きくなったおまさは新悟。(おしんが田中裕子に育ったくらいのギャップがあるぞ)
平蔵は再び幸四郎。妻に雀右衛門。幸四郎だと話の内容が気恥ずかしい。吉右衛門ならそうでもないんだろうな。
同心小柳を中車が演っているのは懐かしい。
おまさが火盗のために働きながら四季が移り変わり江戸の物売りたちが行き交う所は、TV版のエンディングを思わせる
同心たちも別の風体に化けて探索をしている。
いい絵柄だ。
(大音量でさつまさが流れる転換にはちょっと笑った 音デカっ)
廣太郎が忠吾でもいいんじゃないかなと思いましたが悪者でした。いい感じの嫌な奴っぷり。
おまさの家で家探しをし手がかりを見つけて走る平蔵が、幸四郎が掴んだ鬼平になっていて良かったな
ツケも剣戟の音もない立ち回りで鬼平苦戦の所へ仲間が到着しどうにか落着。あの女の情人が斬れるかのセリフは欲しかった。でも幸四郎だと気恥ずかしいかな、
彦十役が又五郎なのだけど、「てっつぁん」「まぁちゃん」と呼ぶ詰まった江戸訛りの一言が江戸家猫八の彦十とそっくりで、その小さい佇まいも彦十過ぎる。でも顔を見ると鋭い眼光の又五郎。すごいな。又五郎もテレビ版出演組なので、リアルに見ていたのでしょうね。
幕切れ、花道を歩く平蔵のバックに、ジプシーキングスのインスピレイション(原曲)が流れます。吉右衛門版のED曲です。時代劇のエンディングは演歌などが多い中ギターのインストがおしゃれで、映像も主人公ではなく江戸(京都だけど)の四季という風情のあるものでした。この曲を引用して吉右衛門版へのリスペクトですよと改めて示して閉じる形です。
今年は秀山祭が菅原の通しなので、このようなアプローチが七月にきたのかしら。
近くの席の人が、普通の鬼平は捕物だけど今回はおまさとの話じゃん、って言ってらして
ああ、と初めて気づきました。
捕物の面白みがある鬼平としての鬼平もいずれあると良いですね。
芝居として面白かったのは、猿弥・宗之助の悪者夫婦や幕間後後半だったので、このテイストで一本やるといいかも。
テレビから来ていた表現は私は面白かったけど知らない人にはどう見えたのかな。
血筋のために呼び戻され家を継ぐことになる銕三郎の苛立ちを、いずれ高麗屋を背負うさだめの染五郎が演じる二重写し的なものを脚本家としては意識したようですが、個人的にはあまり感じられず。染五郎は好きで芝居してそうだもの。
蝶の道行
染五郎、團子のコンビで。
團子の女形を見るのは私は初めてかも。
うまいというのではなく、この関係と渾身の姿勢から感じられるものを皆褒めているのかなと思いました。
幕切れの所が印象に残るけれどそこは物語が見える所ゆえでした。
新橋演舞場
歌舞伎 刀剣乱舞 東鑑雪魔縁
刀剣乱舞歌舞伎の2作目が新橋演舞場で上演されました。
えー、個別のあれこれを書いたら長くなりすぎたのでそれは発酵棚に置いといて。
こんな歌昇お得パックになるとは思わなかったというのが総括です。
2作目を前と同じフォーマットではやらない
あんな歌舞伎こんな歌舞伎の楽しみは大喜利所作事にパッキングされ、
お芝居側は、語りや踊りが急に混ざってくる義太夫狂言風の場面やゆっくりした所作ダテや幕外の出語りなど古い歌舞伎の様式を避けて、
前のような新歌舞伎かと思えば突然古典になるような編成ではなくなりました
見る側は古い歌舞伎から脱出しようとした明治の歌舞伎のどこが新しいのかが感じられない21世紀の民であり、わかりやすい古い様式をとっぱらっちゃうと逆に「普通」に近づくベクトルになります
様式で変化が出ないので、芝居そのものに負う所が大きくなりますが、
初日近くは平板に感じました
言葉を選ばずに言えば軽い失望があった
前回もっとわくわく面白かったなって。
ところが、見るたびに変わる
同じ本でここまで変わる?と思うくらいに化けました
特に実朝の歌昇が階段の場面などで濃い芝居を始め、
他の役の芝居の温度やたっぷり度合いの基準がそのレベルに追随して上がっていったような。
歌昇は陸奥守を含めちょい先にいきすぎたのか基本に戻ってきたとこもありますが、
最後に緩急が出てきたのが、膝丸と実朝の問答と、公暁の闇堕ちの辺り。
実朝が自分の理想とするまつりごとについて語る所で私の見た回では楽の1日前で初めて拍手が来ました。
膝丸そんな簡単に教えていいんかーいと思っていた所も倩子姫の頭を地面に擦り付けんばかりの懇願があって初めて噛み合う。
やっとかぁ
もう新橋のひと区切りまで来てしまったよ、というのが今である。
(若者たちに松也っぽい粘り気が出てきてるのが面白い。伝染るのか演出なのか。)
これは初日に見た人と最後に見た人でだいぶ評価が違うでしょうね。多分ひと月後はまた変わるでしょう。
それとは別に、
最後の闘いは刀と(元)あるじで一騎打ちししっとりと泣かせた前作と、
愁嘆場は先に済ませて乱戦から整然とした立ち回りまで戦闘パートをがんがん入れて全員で決着の今作と、構成の好みが分かれた部分もあったようで。私は物語の切れとしては前作が好きなんですよ。でも歌舞伎アクションショーという意味では今回グッジョブ。
あと、コンテンツの性格上刀剣男士への思い入れのありやなしやで全然見えてるもんが違うんだろうと思うけど
百年後に残るとしたら経緯は消えて芝居しか残んないだろうから、知識なしで見て面白いかどうかはやっぱ大事だよなあ…と、かの「高時」を見て思います。
もっと書きたいことはありますが、いずれ改めて。
大喜利所作事 舞競花刀剣男士
踊り楽しかったです。
源氏兄弟で三番叟風の剣舞、三日月宗近の男伊達、夏の浴衣で陸奥守、同田貫、加州メインのご当地の踊り、三日月・小烏丸で扇の的、鬼丸国綱と精四郎・蔦之助コンビでの石橋、最後に近侍曲で各男士単独の踊りの後、全員で時を超えてを踊り、綺麗に並んで暗転の後、刀の姿に戻っているという見立て。
那須与一のやつが好きです。この踊りは花外からの景色が良かった。花道で弓を構えた与一と舞台上の扇の的が一直線に見えて、
放った、扇が舞った、の連携が見えました
陸側になったり、海側になったり回り込んだりを役者の移動で見せるのも
義太夫と琵琶の掛け合いも良かった
あとよさこい節。歌昇/陸奥守の所作板を踏み鳴らす音と一緒に思い出されます
足が心配になるくらいの音がしてましたが、配信だと生音を絞ってるのか黒御簾の太鼓の音も所作板の音も全然聞こえませんね。
現地やっぱり良いですよ。
8月の公演へもお客様が沢山足を運んでくれますよう
(ラスト、江戸千穐楽だけ「『当月』の我が歌舞伎本丸においての我らが役目」って言ってるんだけど、大千穐楽はなんて言うかな。)