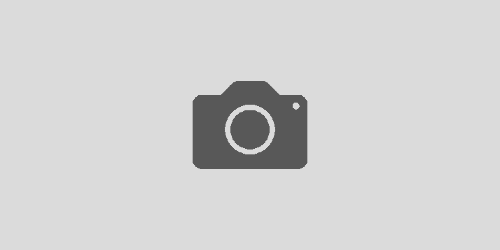とうかぶ宗近殿の男伊達(勝手解釈的なもの)
舞競花刀剣男士(まいきそうはなのつわもの)の春の踊り”男伊達”の聞こえた部分の歌詞による勝手解釈です。
#歌詞は耳コピにて。そのうち大千穐楽の配信で補完…気が向けば上演台本を読みに行きたし。
筋書やガイドによれば三日月宗近が元の主人を思いながら京のゆかりの地を巡るという趣向
桜柳の春錦…
柳桜の春錦 八重の霞にいや高きめぐりに何か音羽山
踊りは、すぼめた傘に頭を隠して下駄を鳴らしての出
着流しで帯に尺八を差した男伊達のいでたちで助六の出端を思わせます
バタバタバタと雨音の太鼓の音
助六の歌詞は桜の吉原から始まりますが
こちらは柳に少し廓の記憶を残しながら桜柳の意匠に印象を変え八重の霞に包まれた都に近づく雰囲気があります
音羽山
三日月宗近を演ずる松也丈の屋号音羽屋の由来は、初代菊五郎の父が音羽山に建つ清水寺の側に住まいしており、境内の音羽の滝からとの説があります。
高台寺
ひのかゆかし高台寺
高台寺は三日月宗近の持ち主であった高台院(北政所)ゆかりの寺です。筋書きには三日月宗近が高台寺から知恩院を巡る旨の記載がありますが唄に知恩院の名ははっきり出ません。ただその後に葵葉の歌詞が来るのでそれが暗示なのでしょう。知恩院は徳川ゆかりの寺で紋は三つ葉葵です。掲げられた紋を見て”髪の葵葉”に連想が至ったのかもしれません。
高台寺、知恩院ともに枝垂れ桜のある名勝で、先の桜柳の歌詞ともイメージが重なってくるように思います。
高台寺の前がいまいち聞き取れませんが「檜の香 ゆかし」ではないか。
振りは傘を開いたまま前面に見せて、三日月に見えるようにしています。
かみの葵葉なつかしく
かみの葵葉なつかしく 散り添う桜にひかされて
葵祭の葵桂の髪飾りのことかと思います。
なつかしくの直訳は心をひかれてで、普通ならいとおしさのニュアンスを感じます。が、三日月さんなので昔と変わらぬ葵の髪飾りにいにしえを重ねて思う風情でしょうか。なんなら三日月宗近の髪の双葉も連想します。そこにひらりと降りかかる桜花。
髪の葵葉のくだりは新橋では節が付いてた気がしますが、京都では、語るかたちでした
※かみは「髪」を採りました。知恩院はお寺なので神ではなかろうと思う。
ほんの真似事丹前六法
歩む形はほんの真似ごと丹前六法 エー つなもなや
散る桜を眺めながら伊達男を気取って丹前六法で歩いてみてるのですかね
月明かりを頼りによもすがら歩いていくのと、よもすがら酒を汲むのがシームレスにかかっていく
振りは、右手で傘を持ち左手で縁を持って、脚を大きく割ってにじる。
#丹前六法の後の歌詞は聞き取れてません。
月の雫のその酒を
朧の月をたのみによもすがら月の雫のその酒を汲みてつきせぬ月見酒
月にちなむ歌詞が並ぶ月づくしの趣向です
夜通し溢れる月の光に酒を酌みながら…なんとなくですがひとりお月様を相手に飲むのでしょう
この辺り閉じた傘の雫を払いながらくるくるとのの字を書いたり開いた傘を車輪のように回す振りがありますが
宗近さんは特に若いもんと戦ったりはしないので優男に見えます
おくる文月 ぬし様参る
このフレーズは端唄にあり。送る文(手紙)と文月(七月(旧暦の七月は今の八月頃、季節は秋です))を掛けている。〇〇様参るは宛先で、”主様参る”は貴方に宛てたということ。宗近殿の振りでは指折り数えて泣いています。
貴方様に文を送り七月の日々をおくりましたといったところか。(けど振りから察するに、この主様は再び来なかったんでしょうね。)
刀としては、幾人もの帰らぬあるじを思って涙するのでしょう。
胸に差し込む三日の月
こころでながむ真如の月と胸に差し込むみかの月
満月の曇りなき境地を思いながらも切なく差し込んでくる三日月のかげもあるというようなことか。
あるいは、差し込んでくる三日月の光に想う、全きまことの月か。
真如の月では勇ましく踏み出しますが、俯き刀の柄に手を添え、水に映った月を見て空の月を見上げ、目線を落とし少し揺れる心がある様子。
しんぞ命を粟田口
しんぞ命の粟田口これ宗近が名作と風情なりける次第なり
助六の唄の結びに「しんぞ命を揚巻のこれ助六が前渡り風情なりける次第なり」とあるもののもじりでしょう。揚巻は助六の恋人。命をあげ(る)と掛かる。粟田口は三条小鍛冶宗近の居と伝わる地。
しんぞは揚巻の文脈では新造でしょうか。この歌では三日月宗近が新造されたことも掛けているか。
また「命を」でなく「命の粟田口」となっており、「ぞ命の『あ』」まで聞くと、赤星十三郎の「今日ぞ命の明け方に消ゆる間近き星月夜」も思い出します。(この辺り、百人一首みたいなもので)
泡のような命で消えそう?もう明け方でしょうか。
これぞまさしく宗近の名作と眺める景色も
その宗近の名作とは私ですよ的な誉れも感じます
“しんぞ命の粟田口”の振りは肩で風を切る丹前六方で男伊達の風情、”これ宗近の名作と”の所は落とし差しにした刀の柄に手を置きます
南座では、”しんぞ命の粟田口これ宗近が名作と風情なりける” までその場で六方の手振りと足踏みを続け(走らないやつです)、”次第なり”で、傘を開いて肩に担いで見得。
(なんか全然違うんで新橋の記憶が怪しくなってきました)
そして強くなった雨音に、宗近殿はまた傘に姿を隠して都を後にします。
新橋で何回か見た後、南座で改めて見ましたら、特に最後の所など、力強く、男伊達っぽくなっていました。これは歌いかたが変わっているのも関係していて、朧な春のそぞろ歩きの宗近から、強い男の印象になったように思います。