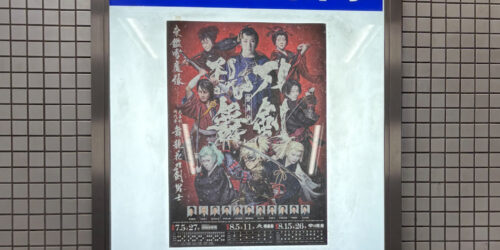2025年8月に見たもの(南座とうかぶ、稚魚、研辰、などなど)
音と動きがかみ合うしあわせという点が結構共通していた葉月でした。 [stoc] 稚魚の会歌舞伎会合同公演 2025.8.14〜8.17 浅草公会堂 引窓、棒しばり、勢獅子の三本 引窓 義太夫と所作と台詞が気持ちよく合い連鎖する引窓 義太夫狂言はそうできているのだとわかります その仕組みが生きるようにやっていることが好もしい よいものを見ました 母お幸は好蝶。中が若い人であることもわかりつつ老母であることも納得させる感触。 女房お早の春江はせりふに少し拙さがありますが慣れの問題かも 新八の濡髪はよい男で、相撲……